皆さんこんにちは!
今回は文化史シリーズ第4弾、平安時代の弘仁・貞観文化を解説します!
平安時代の文化と聞くと、貴族の華やかな文化を思い浮かべる方が多いと思います。
和歌や仮名文字などの華やかな文化は「国風文化」と言い、平安時代の中期に栄えた文化です。
今回は平安時代初期に栄えた、弘仁・貞観文化を詳しく見ていきます!
↓奈良時代の文化を復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓
弘仁・貞観文化とは?
時期・中心地・背景
弘仁・貞観文化の最盛期は、9世紀です。
「桓武天皇・嵯峨天皇」の時代を中心に発展しました。

〈桓武天皇:Wikimedia Commons〉
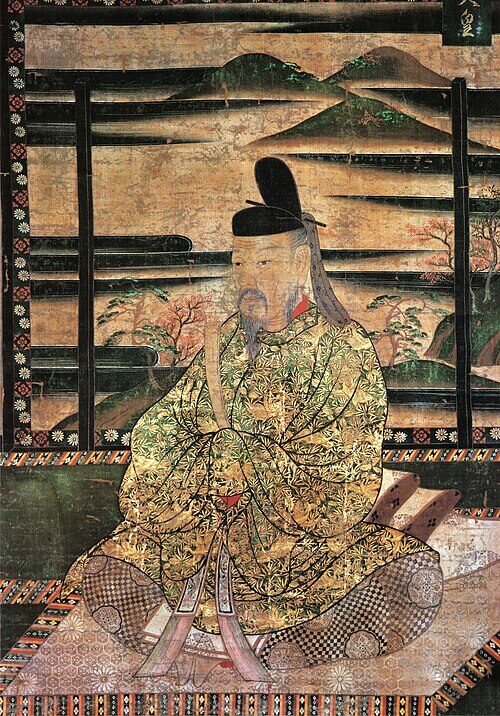
〈嵯峨天皇:Wikimedia Commons〉
平安時代の都である「平安京」が中心地です。
遣唐使の派遣による、晩唐文化の流入が文化発展のキッカケです。
特色
- 密教の影響で山岳地帯に伽藍造営、密教彫刻・密教絵画が登場
- 唐の影響で、唐風の書が生まれる
- 漢詩文が発達
平安仏教
最澄・空海
「桓武天皇」に遣唐使に取り立てられた事で、日本史を変えた2人の天才です。
彼らの詳細を表にしたので、こちらをご覧ください!
| 項目 | 最澄(さいちょう) | 空海(くうかい) |
|---|---|---|
| 生没年 | 767~822年 | 774~835年 |
| 出身地 | 近江(滋賀県) | 讃岐(香川県) |
| 遣唐使 | 804年に唐へ | 同じく804年に唐へ |
| 学んだ宗派 | 天台宗 | 真言宗 |
| 中心寺院 | 比叡山延暦寺(ひえいざん えんりゃくじ) | 高野山金剛峯寺(こうやさん こんごうぶじ) |
| 教えの中心 | 一乗思想(すべての人が仏になれる) | 即身成仏(生きながら仏になれる) |
| 別名・尊称 | 伝教大師(でんぎょうだいし) | 弘法大師(こうぼうだいし) |
| 著作 | 顕戒論(820年成立) 南都六宗の反対に対し、大乗戒壇設立の正統性を記した | 三教指帰(797年成立) 「仏教」が「儒教」・「道教」よりも優れていると説く |
| 特徴 | 戒律を重視、僧侶の独立(大乗戒)を主張 | 儀礼・呪文・修法などの密教的実践を重視 |
| 国家との関係 | 桓武天皇の信任を得て延暦寺を開く | 嵯峨天皇に重用され、教王護国寺(東寺)を与えられる |
| 密教 | 最澄の弟子の円仁・円珍が密教化を進める | 本来密教であり、加持祈祷が中心 |
| 密教の別名 | 台密 | 東密 |
| 関連する項目 | 円仁と円珍が対立し、寺門派(円仁)と山門派(円珍)に分裂 | 庶民教育のための綜藝種智院の設立 |
| 後世の影響 | 法然・親鸞・道元・日蓮・栄西が比叡山で学び、鎌倉新仏教を生む | 密教文化(曼荼羅・護摩・儀式)を日本に根付かせる |
最澄

〈最澄:Wikimedia Commons〉
始めた宗派:天台宗
中心のお寺:比叡山延暦寺(滋賀県)

〈比叡山延暦寺:Wikimedia Commons〉
考え方:すべての人に仏になれる可能性がある
著作:顕戒論(820年成立)
最初空海と仲良しでしたが、喧嘩して絶縁状態になりました(笑)
最澄は唐から帰国した後、天台宗を開きました。
天台宗は「一部の人だけでなく全員が仏になれるので、その為に毎日仏教の修行をしましょう!」という考え方です。
天台宗は本来、「密教」ではありません。
しかし、「最澄」の弟子である「円仁」・「円珍」が密教化を進めました。

〈円仁:Wikimedia Commons〉

〈円珍:Wikimedia Commons〉
空海

〈空海:Wikimedia Commons〉
「弘法筆を選ばず」の「弘法」は空海を指します。
始めた宗派:真言宗
中心のお寺:高野山金剛峰寺(和歌山県)

〈高野山金剛峰寺:Wikimedia Commons〉
考え方:生きたまま仏になれる
著作:三教指帰(797年成立)
最澄の弟子が空海の元に勉強に行くと、魅力的すぎて帰ってこなかったと伝わっています。
空海は唐から帰国した後、真言宗を開きました。
空海の考え方は、「「死後の世界を期待してもしょうがない」です。
生きている内にご利益があるからこそ意味があるという考えの元、真言宗を始めたのです。(筆者もそう思う、死後じゃなくて今利益が欲しいよね)
真言宗は天台宗と同様、毎日修行する事が良いとされています。
「真言宗」は元から「密教」の考え方です。
仏像
弘仁・貞観文化の仏像の特徴は、「一木造」です。
その名の通り、一本の木を削り仏像を完成させます。
その為ミスが許されません。
観心寺如意輪観音像
これだけは覚えてくれ!って言える程、弘仁・貞観文化を代表する仏像です。
密教の神秘的な雰囲気を漂わせています。

〈観心寺如意輪観音像:河内長野市HP〉
「観心寺」は大阪にあります。

〈観心寺:Wikimedia Commons〉
薬師寺僧形八幡神像
「僧形八幡神像」=「僧侶の姿形をもって表された八幡神の像」を指します。
「神仏習合」によって神像が作られました。
「神仏習合」=「日本古来の神と外来宗教である仏教とを結びつけた信仰」を指します。
寺院に神が祀られるなど、神道と仏教の境界が曖昧になっていたのです。
現代を生きる我々も、神様と仏様の違いって曖昧ですよね。

〈薬師寺僧形八幡神像:Wikimedia Commons〉
「薬師寺」は奈良県にあります。

〈薬師寺:Wikimedia Commons〉
教王護国寺講堂五大明王像
中心に座っているのが「不動明王」です。
その周りに「軍荼利明王」・「「金剛夜叉明王」・「大威徳明王」・「降三世明王」が安置されています。
密教の世界観が色濃く映し出されています。

〈教王護国寺講堂五大明王像:Wikimedia Commons〉
「教王護国寺」は別名「東寺」と呼ばれています。
「東寺」は「嵯峨天皇」が「空海」の為に建立したお寺です。

〈教王護国寺:Wikimedia Commons〉
絵画・彫刻
教王護国寺両界曼荼羅
弘仁・貞観文化を代表する作品です。
彩色の両界曼荼羅として世界最古だと言われています。
「両界」=「金剛界・胎蔵界」を表しています。
金剛界曼荼羅
9つに区分され、上の段の真ん中に大日如来が描かれています。
金剛石のように強い大日如来の「徳」が表現されています。
「金剛」=「ダイヤモンド」を指します。
他の部分は、修行者が大日如来の境地に達する過程を表現しています。
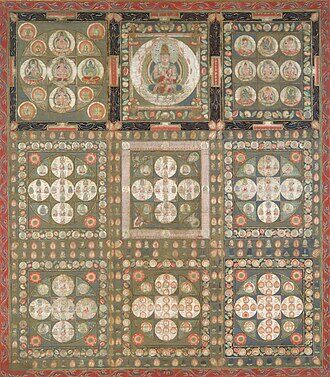
〈金剛界曼荼羅:Wikimedia Commons〉
胎蔵界曼荼羅
中心に蓮華の花を添え、大日如来が描かれています。
全てのものが大日如来から放出されている場面です。
「胎蔵」=「赤ちゃんが母親のおなかで成長するように、菩薩が如来へと進むこと」を指します。
母親の慈悲のように、大日如来が皆を見守っているのです。

〈胎蔵界曼荼羅:Wikimedia Commons〉
黄不動
一般公開されていないものですが、模写の中では最古のものになります。
天台宗の「円珍」が座禅している最中に不動尊が出現し、「帰依するのならば、私が守護しよう」と問いかけたと言われています。
「円珍」は不動尊の姿を、画家に模写させたと言います。
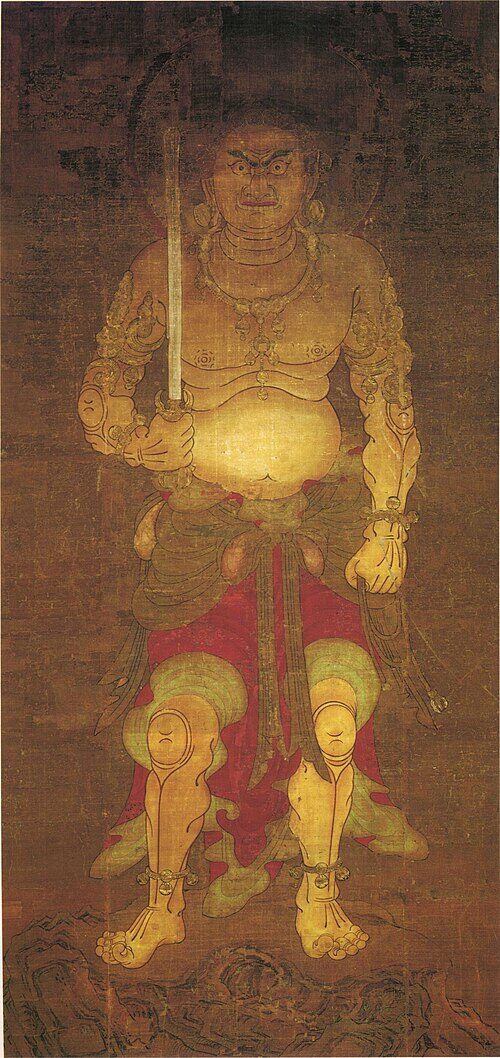
〈黄不動:Wikimedia Commons〉
信仰・教育
修験道
「修験道(しゅげんどう)」=「山岳修行による呪力体得を目指す信仰」を指します。
「修験者」=「山伏」とも言われます。
奈良県の「大峰山」や石川県の「白山」が修験道の代表的な山です。

〈大峰山:Wikimedia Commons〉

〈白山:Wikimedia Commons〉
「山岳伽藍」に籠るというのは、まさしく「天台宗」・「真言宗」を筆頭とする「密教」の影響を受けています。
奈良県の「室生寺(むろうじ)」は、「山岳伽藍」の代表例です。

〈室生寺 金堂:Wikimedia Commons〉
三筆
「三筆」=「嵯峨天皇」・「空海」・「橘逸勢」を指します。
書道が上手い人と認識されがちですが、本当の意味は「唐風の力強い書を残した人」が正確な意味です。
三名の中でも「空海」の残した「風信帖(ふうしんじょう)」は最高傑作と言われ、国宝に指定されています。
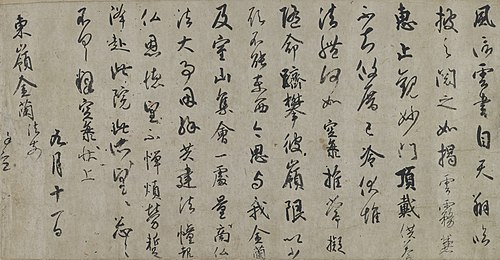
〈風信帖:Wikimedia Commons〉
「風信帖」は「空海」が「最澄」に宛てた手紙です。
大学別曹
「大学別曹」=「有力貴族が子弟の為に営んだ私的な宿舎」を指します。
元々は私的なものでしたが、奈良時代に設立した「大学」の付属機関として公認されました。
「別曹」=「政府が大学生の為に建てた、直曹に対する言葉」を指します。
「大学別曹」は以下が有名です。
弘文院(800年~808年頃)
「和気広世」が設立しました。
「和気広世」は「和気清麻呂」の息子です。
勧学院(821年)
「藤原冬嗣」が設立しました。

〈藤原冬嗣:Wikimedia Commons〉
「藤原冬嗣」は「嵯峨天皇」の蔵人頭に就任したのが有名ですね。
学館院(840年代)
「橘嘉智子」が設立しました。

〈橘嘉智子:Wikimedia Commons〉
「橘嘉智子」は「嵯峨天皇」の皇后です。
奨学院(881年)
「在原行平」が設立しました。

〈在原行平:Wikimedia Commons〉
「在原行平」は「在原業平」のお兄さんです。
↓在原行平は百人一首に選ばれています、こちらもご覧ください↓
綜芸種智院(828年 12月15日)※庶民向け
「綜芸種智院(しゅげいしゅちいん)」=「空海が庶民教育や各種学芸教育を目的に設置した私立学校」です。
当時原則的に、教育機関の「大学」は身分制限があり、殆ど庶民に解放されていませんでした。
空海はその状況は良くないと考えていました。
全学生・教員への給食制を完備した、身分貧富問わず学べる教育施設を創ろうと考えたのです。
その努力の結晶が「綜芸種智院」でした。
文学・日記
勅撰漢詩文集
凌雲集:814年
日本初の勅撰漢詩集です。
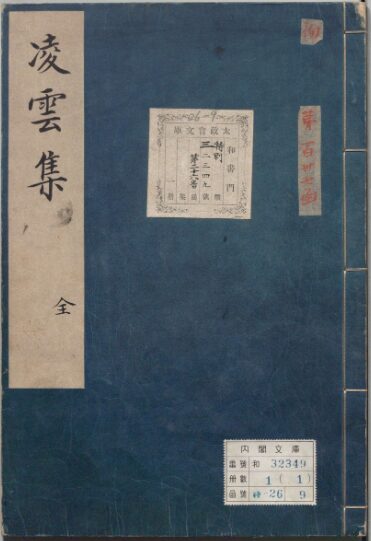
〈凌雲集:国立公文書館〉
「嵯峨天皇」の命で作成されました。
編纂者は「小野岑守」です。

〈小野岑守:Wikimedia Commons〉
文華秀麗集:818年
「凌雲集」に続く漢詩集です。
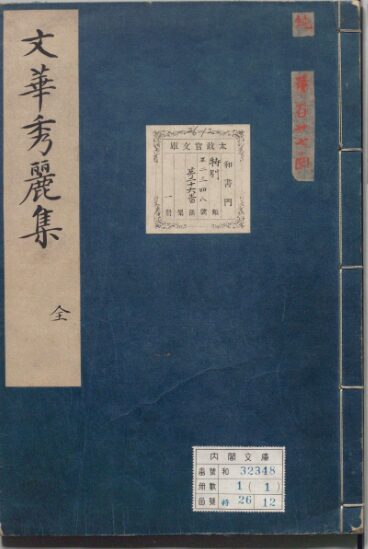
〈文華秀麗集:国立公文書館〉
「嵯峨天皇」の命で作成されました。
編纂者は「藤原冬嗣」です。
通史を勉強した方なら分かると思いますが、「藤原冬嗣」に対する「嵯峨天皇」の信頼が厚すぎます(笑)
経国集:827年
「凌雲集」・「文華秀麗集」と並ぶ勅撰漢詩文集です。
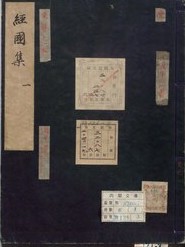
〈経国集:国立公文書館〉
「淳和天皇」の命で作成されました。
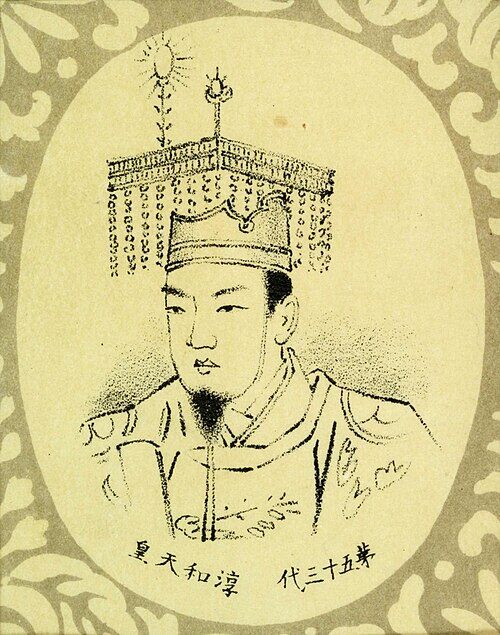
〈淳和天皇:Wikimedia Commons〉
編纂者は「良岑安世(よしみねの やすよ)」と「菅原清公(すがわらの きよきみ)」です。
「良岑安世」は「桓武天皇」の息子で、臣籍降下した人物です。
「菅原清公」は「菅原道真」のおじいちゃんにあたります。

〈良岑安世:Wikimedia Commons〉

〈菅原清公:Wikimedia Commons〉
漢詩文集
性霊集
「空海」の漢詩文集です。
勅撰(天皇の命令)ではないので、個人で作成したものになります。
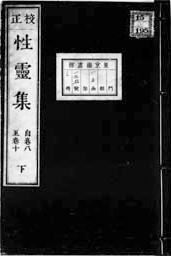
〈性霊集:Wikimedia Commons〉
編者は「空海」の弟子の「真済」です。
史書
類聚国史:892年
「類聚国史(るいじゅうこくし)」=「編年体である六国史の記事を、中国の類書にならい分類再編集した歴史書」を指します。
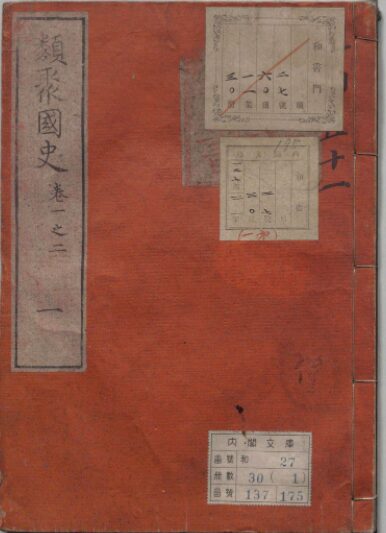
〈類聚国史:国立公文書館〉
↓「六国史」についてはこちらで解説しています!!↓
「宇多天皇」の命で作成されました。

〈宇多天皇:Wikimedia Commons〉
編纂者は「菅原道真」です。

〈菅原道真:Wikimedia Commons〉
日記
入唐求法巡礼行記
「入唐求法巡礼行記(にっとうぐほうじゅんれいこうき)」=「最後の遣唐使として唐に渡った円仁の旅行記」です。

〈入唐求法巡礼行記:Wikimedia Commons〉
意外と遣唐使として派遣されている人物は多いので、表にして確認すると理解が深まります。
学生の方へ
大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。
それが日本史一問一答です。
日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]
今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。
最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。
以下が実際の例題です。
日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、
[★★★]を唱える事によって救われると説いた。
文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。
例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。
私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。
学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。
自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。
早めに対策した者が受験勉強を制します。
さぁ、日本史を楽しみましょう!


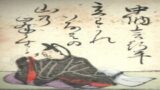

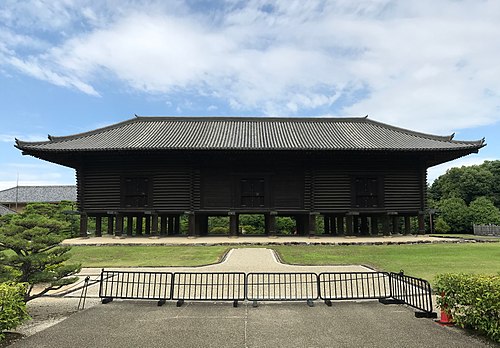

コメント