↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
100番 順徳院(じゅんとくいん) 『続後撰集』
百敷(ももしき)や 古き軒端(のきば)の しのぶにも
なほあまりある 昔なりけり
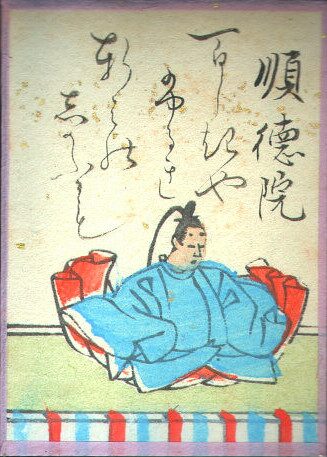
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
宮中(百敷殿)の古びた軒端の忍ぶ草を見るにつけても、
やはり偲んでも偲びきれないほど、懐かしく思い出されるのは昔のことである。
語句解説
【百敷(ももしき)や】
「百敷」= 宮中・内裏(だいり)のこと。
古代から宮殿を指す美称です。
「や」は詠嘆の間投助詞。
【古き軒端(のきば)の】
古びた宮殿の軒(屋根)の端のこと。
荒れ果てた宮中の様子を表現しています。
【しのぶにも】
「昔の栄華を懐かしく思う」という意味の「偲ぶ」と、軒からぶら下がっている「忍ぶ草(ノキシノブ)」の意味の掛詞です。
〈画像:Wikimedia Commons〉
建物の荒廃と天皇(貴族)の権威の衰退を暗示しています。
【なほあまりある】
「なほ(猶)」=「やはり」「それでもなお」の意味の副詞。
「あまりある(余りある)」=「(偲んでも)あり余る程に」という訳。
「偲んでも偲び切れない」という意味です。
【昔なりけり】
「けり」は詠嘆の助動詞。
「昔なのだなあ」という訳。
「昔」は具体的には醍醐天皇や村上天皇の延喜(えんぎ)・天暦(てんりゃく)の治を指します。
藤原氏の権力が圧倒的だった時代にも、この2人の天皇は親政(天皇自ら政治を執る事)を行い、民衆からの評判も良かったと言われています。
作者: 順徳院
順徳天皇(じゅんとくてんのう) 〈1197年 ~ 1242年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
第84代天皇で、在位は1210年から1221年で、後鳥羽天皇の息子です。
↓後鳥羽天皇の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓
承久の乱(1221年)で後鳥羽院側として幕府と対立して敗北し、佐渡島に配流され生涯をそこで過ごしました。
↓承久の乱について解説しています、こちらもご覧ください!!↓
自らの帰京と子孫への皇位継承に対する幕府の強い拒絶の意思を知った上皇が絶食による事実上の自殺を図ったと言われています。
政治的には短期間の在位ながらも、院政期の文化的・政治的背景を色濃く反映する人物です。
政治的な困難や流罪という過酷な環境の中でも、文化や文学に深い関心を持ち、歌学書「八雲御抄(やくもみしょう)」を残しました。
生涯を通じて、政治的挫折や孤独な環境が彼の作品に反映されており、自然や宮廷の往時を偲ぶ感情、人生の無常観、郷愁などが深い味わいを持つ歌風として評価されています。
鑑賞:失われた貴族の隆盛、彼が見たものは🏛️
かつての栄華を誇った宮中の面影を前にして、過ぎ去った時代への懐古の情を詠んだ作品です。
歌の冒頭「百敷や」で、広大な宮殿を思い浮かべつつ、古びた軒端の「しのぶ草」に目を留めます。
この「しのぶ」は「偲ぶ(しのぶ)」の掛詞として、過去を懐かしむ心情を象徴しており、偲ぶ草との掛詞に注目です。
「なほあまりある昔なりけり」という結句で、宮中の景色を眺めるだけでは慰めきれないほど、かつての栄華や出来事への思いが心にあふれていることが示されます。
荒れた庭や古びた建物の描写を通して、順徳院自身の政治的挫折や貴族の隆盛が失われていく悲しさが静かに表現されています。
この歌の魅力は、目に見える風景と心の内面を自然に重ねる手法にあります。
古い軒端のしのぶ草を見る行為自体が、過去を思い出す契機となり、読み手に自然と郷愁や無常観を感じさせます。
順徳院の置かれた状況や人生観を背景にすると、深い哀感と静かな叙情が漂う一首となっています。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた





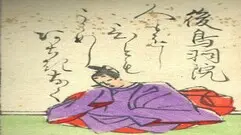

コメント