↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
98番 従二位家隆(じゅにいのいえたか) 『新勅撰集』
風そよぐ ならの小川の 夕暮れは
みそぎぞ夏の しるしなりける
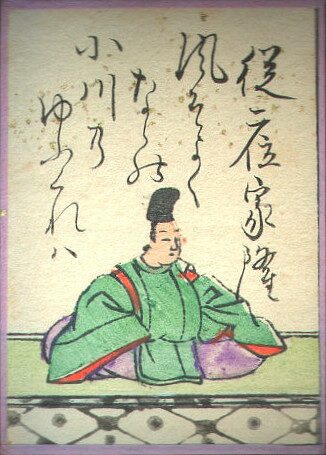
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
風がそよそよと吹いて楢(なら)の葉を揺らしている。
ならの小川の夕暮れには、六月祓のみそぎの行事こそが、夏である事を示しているのだなあ。
語句解説
【風そよぐ】
そよそよと柔らかく吹く風のこと。
涼しさや静けさを感じさせる表現。
【ならの小川】
京都の下鴨神社の境内を流れる「御手洗川(みたらしがわ)」のこと。
「なら」は境内にあるブナ科の落葉樹である楢(なら)の木に由来するとも、地名「奈良」に掛けたともされています。
【夕暮れ】
日が沈む頃を指します。
涼しい風や柔らかな光など、しみじみとした情緒を伴う時間帯。
【みそぎぞ】
「みそぎ」は「六月祓」の事を指します。(動画もあるので、ぜひ調べてみて下さい)
「旧暦」の6月30日(現在だと8月上旬)に六月祓(みなづきばらえ)=夏越の祓(なごしのはらえ)を行い、1月から6月までの罪や穢れを祓い落とす行事が行われました。
「ぞ」は強意の係助詞。
【夏のしるしなりける】
「しるし」は「証拠」という意味です。(現在でも使いますね)
「けり」= 詠嘆の助動詞の連体形で、みそぎぞの「ぞ」と係結びになっています。
「まさにで夏の証拠だなあ」と、気づきやしみじみした感情を込める表現です。
作者: 従二位家隆
藤原 家隆(ふじわらの いえたか) 〈1158年 ~ 1237年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
鎌倉時代初期の公卿・歌人で、寂蓮法師の家に婿として入り、藤原俊成に歌を学びました。
↓寂蓮法師の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓
家隆は宮廷に仕える公卿でありながら、和歌の道に深く専念し『新古今和歌集』の撰者の一人としても活躍しました。
家隆の歌風は簡潔で叙情的、自然描写と心情表現が一体化しているのが特徴です。
季節の移ろい、日常の風景、恋や人生の無常を巧みに取り入れ、読み手にしみじみとした感情を呼び起こします。
また、自然の小さな現象や具体的な風景を通して、自らの内面の感情や人生観を象徴的に表現する手法を得意としました。
政治的には公家として朝廷に仕え、権勢を振るう立場にありましたが、権力や地位よりも和歌の価値を重視し、晩年まで創作を続けました。
その作品は後世に大きな影響を与え、鎌倉時代以降の和歌の基本的な感性や技巧の形成に貢献しています。
鑑賞:季節の移ろい、六月祓はまだ⛩️
「ならの小川」を舞台に、夏の終わりを告げる夕暮れの情景を詠んでいます。
「風そよぐ」は、葉ずれの涼しい音を感じさせ、盛夏の暑さから秋へと移りゆく気配を暗示します。
「なら」は地名であると同時に「楢(なら)の木」の葉を思わせ、聴覚と視覚の両方に涼感を与えます。
「みそぎ」は、旧暦六月晦日に行われる夏越の祓(なごしのはらえ)のこと。
半年間の罪や穢れを祓い清めるこの行事は、暦の上で夏の節目を示すものでした。
家隆は、この小川で人々がみそぎを行う光景を目にして、「ああ、これこそ夏のしるしなのだ」と感慨を込めています。
この歌の魅力は派手な感情表現を避け、さりげない風景描写の中に時間の移ろいと季節の節目を静かに感じ取らせる点にあります。
夕暮れという一日の終わりと、夏越の祓という半年の終わりが重なり、時間と季節の交差点が詩情豊かに描かれています。
家隆らしい簡潔な言葉選びと音の心地よさは、読み手に清涼感と静かな余韻を残し、まるでその場の涼しい風や川のせせらぎまで感じさせる一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


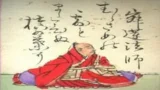
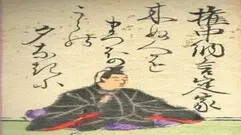
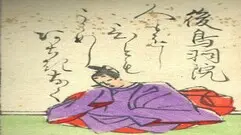
コメント