↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
96番 入道前太政大臣(にゅうどうさきのだいじょうだいじん) 『新勅撰集』
花さそふ 嵐の庭の 雪ならで
ふりゆくものは 我が身なりけり
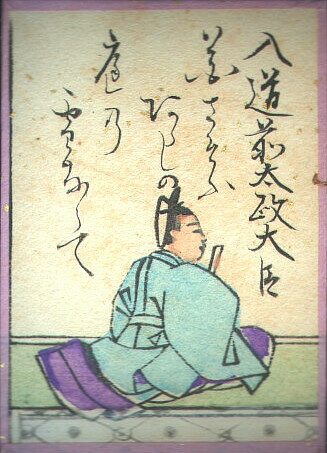
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
花を誘って散らす嵐が吹きすさぶ庭に降っているのは雪ではない。
降り積もっていくのは他でもなく、この私の年齢(老い)なのだなぁ。
語句解説
【花さそふ】
「嵐が桜を誘って散らせる」という意味。
「花」は基本、桜の事を指します。
〈画像:Wikimedia Commons〉
【嵐の庭の雪ならで】
「嵐」は山から吹き下ろす激しい風の事。
桜の花びらが舞い散る情景です。
「なら」= 断定の助動詞 +「で」= 打消の接続助詞で、逆説の仮定条件を表します。
「嵐が吹く庭の雪ではなくて」という意味です。
【ふりゆくものは】
「ふる」=「降る」と「経る(時が過ぎる)」の掛詞です。
「桜の花びらが降る事」と、「自分が年を取っていく事」を重ねています。
【我が身なりけり】
「なり」は断定の助動詞「なり」の連用形、「けり」は詠嘆の助動詞。
「降って積もっていくのは我が身(=老いゆく自分)であった」の意味。
気づけば歳月が過ぎ、老いが積もっていったことを嘆く結びです。
作者: 入道前太政大臣
西園寺 公経(さいおんじ きんつね) 〈1171年 ~ 1244年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
鎌倉時代前期の公卿であり歌人で、百人一首の撰者・藤原定家の義弟です。
建保7年(1219年)には関白に就任し、鎌倉幕府とも良好な関係を築きながら、朝廷と幕府の協調に尽力しました。
しかし1221年、後鳥羽院と順徳院らが幕府転覆を企てた承久の乱の時、計画を知って幽閉されましたが、幕府に漏らして乱を失敗に終わらせました。
↓承久の乱ついて解説しています、こちらもご覧ください!!↓
この功績が讃えられ、太政大臣まで出世しました。
また、政治家としてだけでなく文化人としても優れており、『新古今和歌集』や『続後撰和歌集』などに多くの和歌が収められています。
晩年は出家し、仏教的無常観や老いの感慨を題材にした作品を多く残しました。
鑑賞:自然からの気付き、散り行くものは🌸
嵐が庭の花を散らしている様子を、人生の無常になぞらえた一首です。
表面上は春の嵐により庭の花びらが散っていく情景を描いた風流な歌ですが、その中に強い人生観が込められています。
前半の「花さそふ 嵐の庭の 雪ならで」では、花を散らす嵐を雪が降っているかのように見立てています。
後半の「ふりゆくものは 我が身なりけり」で、その情景を人生と重ね合わせています。
「ふりゆく」は「降り行く(花びらが降る)」と「経ゆく(時が過ぎ、老いていく)」を掛けた言葉で、花びらの散りゆく様子から、自らの老いと人生の終わりを悟る心情を表しています。
この歌の背景には、西園寺公経が晩年を迎えた時期の感慨があると考えられます。
公経は鎌倉時代前期の公卿で、政治の中枢で活躍しつつも、度重なる政変や時代の移り変わりを目の当たりにしました。
権力も栄華も永遠ではなく、やがて人も花のように散っていくという無常観が、この短い歌に凝縮されています。
華やかな宮廷生活を送ってきた人物が、自らの人生の黄昏を花の散る情景に重ね合わせたこの歌は、自然描写の美しさと深い人生の悟りが同居しており、鎌倉時代の和歌の中でも特に余韻の深い一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた




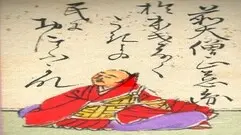
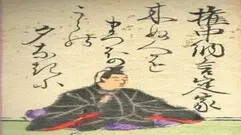
コメント