↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
95番 前大僧正慈円(さきのだいそうじょうじえん) 『千載集』
おほけなく うき世の 民に おほふかな
わがたつ杣(そま)に 墨染(すみぞめ)の袖
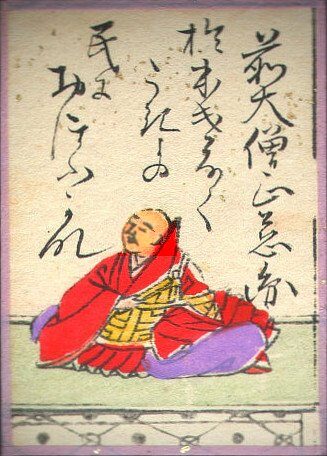
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
身の程をわきまえぬ事ではあるが、つらく苦しい世の中の人々に、包み込みたいものだ。
私が出家して住むこの山の杣(木こりの里)で着る、僧衣(墨染め)の袖を。
語句解説
【おほけなく】
「身の程知らずに」、「おそれ多くも」という意味。
作者は関白の息子でしたのが、ここでは謙遜の意味が込められています。
【うき世の民(たみ)】
「つらく苦しい世の中の人々」のこと。
「うき世(憂き世)」は現世の苦しみ多い世界を意味します。
彼が生きた時代は、保元・平治の乱が発生し、「末法」と言われ閉塞した時代でした。
【おほふかな】
「覆ってやりたいものだなあ」という願望を表します。
「かな」= 感動・願望の終助詞。
作者は僧なので、仏の功徳によって人民を救い祈ることを指しています。
「おほふ」は「袖」と縁語です。
【わがたつ杣(そま)に】
「私が住む山里に」という意味。
「杣」= 木を切り出す杣山(そまやま)のこと。
今回は比叡山(下の写真)を指しています。
〈画像:Wikimedia Commons〉
比叡山の根本中堂(こんぽんちゅうどう)を建てるときに最澄が詠んだ「我が立つ杣に冥加あらせ給へ(私が入り立つ杣山に加護をお与えください」という歌からインスピレーションを得ています。
↓比叡山、最澄について解説しています、こちらもご覧ください!!↓
【墨染(すみぞめ)の袖】
出家僧の衣服の色である黒や濃灰色の袖。
「墨染」と「住み初め(住みはじめること)」の掛詞になっています。
自分の出家の身を象徴し、世の人々を覆う(助ける)象徴です。
作者: 前大僧正慈円
慈円(じえん) 〈1155年 ~ 1225年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての天台宗の僧で、法性寺関白藤原忠通の子として生まれました。
↓法性寺関白藤原忠通の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓
幼少期から宮廷に仕え、朝廷の政治や文化に深く関わった経歴を持つ一方、出家して天台宗の僧として修行し、後には前大僧正(天台座主)にまで上り詰めました。(足利義教も天台座主になっていますね)
和歌においても優れた才能を発揮し、『拾遺愚草』や『玉葉』などの歌集に作品が収められています。
自然や四季の情景を通して、人生の無常や人々への思いやり、出家者としての心境を表現する作品が多く、平安末期から鎌倉初期の歌壇において重要な位置を占めています。
日本初の歴史論集「愚管抄」の作者でもあり、大学受験で日本史選択の方には絶対に覚えてほしいです。
また、政治・宗教・文学の三方面で活躍したことから、鎌倉時代初期の文化を理解する上で欠かせない人物の一人とされています。
鑑賞:閉塞した時代、人々救済したい🧘♂️
出家者としての慈円の謙虚な心と、世の人々への深い慈悲の心が象徴的に表現されている点が魅力的な一首です。
冒頭の「おほけなく」は、自分の願いや行動が身分に過ぎることを謙遜する表現であり、出家者としての慎み深さを示していますが、その謙遜の裏には、「うき世の民におほふかな」という、人々の苦しみを少しでも和らげたいという強い思いが込められています。
「おほふ」という言葉には、「覆う」「保護する」という意味があり、物理的ではなく精神的・象徴的な救済の意志が込められています。
「わがたつ杣に 墨染の袖」の「杣(そま)」は山林や山里を意味し、俗世を離れた静かな生活の場を示し、「墨染の袖」は僧衣を象徴し、出家者としての立場から戦で荒れた世の人々を守り、仏の教えを示したいという思いを暗示していると考えられます。
この歌は20代の頃の作者が、伝教大師の歌を本歌としてふまえ、自らの使命感と理想を高らかに詠んだ一首で、若さの大志にふさわしい歌でしょう。
70歳で亡くなった作者ですが、その崇高な想いは叶ったのでしょうか。
時代は武士の世の中に変化し、人々は翻弄されましたが、そんな人々の救いになっていれば、彼も本望でしょう。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた



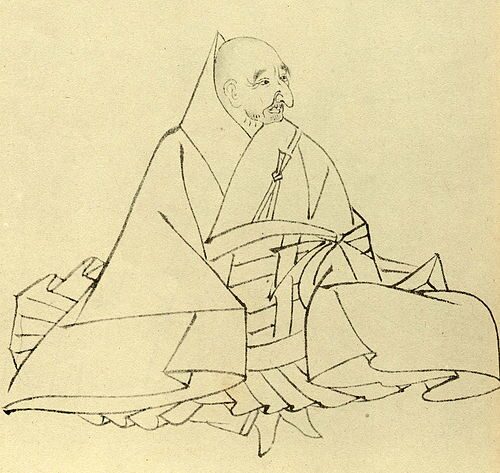

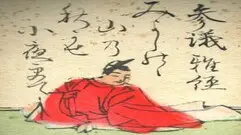

コメント