↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
82番 道因法師(どういんほうし) 『千載集』
思ひわび さても命は あるものを
憂きに堪へぬは 涙なりけり
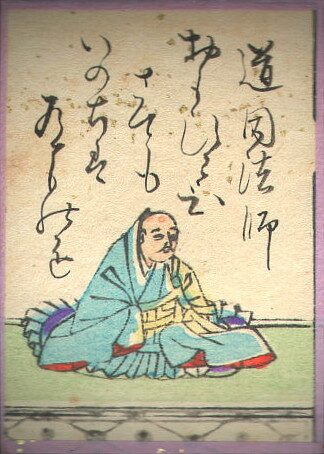
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
つれない人のことを思い嘆きながら、それでも命はまだあるのに、
つらさに耐えられないのは涙であるよ。
語句解説
【思ひわび】
「思い悩み、苦しみ続ける」という意味。
強い心の疲れや悲しみを表します。
【さても】
「それでも」「それなのに」という意味。
逆説を表す言葉です。
【命はあるものを】
「ものを」は逆接の接続助詞。
次に出てくる「涙」に対して、「命は死なずに残っているのに」というような意味を表します。
【憂きに堪へぬは】
「憂き」=「つらい」「悲しい」「苦しい」という意味の形容詞「憂し(うし)」の連用形。
「に」は格助詞です。
「堪へ」=「堪ふ」の未然形で「こらえる」という意味です。
「ぬ」は打消の助動詞「ず」の連体形。
【涙なりけり】
断定の助動詞「なり」+ 過去の助動詞「けり」。
「涙だったんだなあ」というような意味を表す。
作者: 道因法師
藤原 敦頼(ふじわらの あつより) 〈1090年 ~ 1182年〉
平安時代中期に活躍した僧侶であり、本名は藤原 敦頼です。
彼は主に仏教の修行をしながら和歌を詠み、その作品には心の内を素直に表現したものが多く見られます。
華やかな宮廷生活とは距離を置き、静かで落ち着いた感性から深い悲しみや寂しさをテーマにした歌を数多く残しました。
彼の歌は人の心の儚さや無常の感覚を繊細に捉え、平安時代の和歌の中でも独特の静謐さを持っています。
鑑賞:報われない恋の悩み、命ある限り😣
強い苦悩とそれに伴う孤独感、そしてそれを超えた繊細な生への執着が複雑に絡み合った感情を見事に表現しています。
まず「思ひわび」と、心の底から絶え間ない悲しみと苦しみに押しつぶされそうな自分自身を告白しています。
その苦悩は単なる一過性のものではなく、長く続く精神的な疲弊を感じさせます。
にもかかわらず、「さても命はあるものを」という一節からは、どこかで生き続けることへのかすかな希望や、命の尊さへの執着が見え隠れします。
これは絶望の淵にあってもなお、人生の根源的な価値を見失わない人間の強さを示しています。
しかしその強さも、涙という形で感情が溢れ出ることで脆くも崩れ去ってしまうのです。
「憂きに堪えぬは涙なりけり」という結びは、理性や覚悟では押さえきれない深い悲しみが、身体の反応として自然に現れる様子を切実に伝えています。
涙は心の叫びであり、誰にも見せられない弱さの象徴でもあります。
この歌は、人間の心の内側にある矛盾と葛藤を繊細に掘り下げ、苦しみながらも生きることの切なさと美しさを見事に映し出しています。
読者は詠み手の涙に共感し、自身の心の奥底にある弱さや悲しみと向き合うきっかけを与えられるでしょう。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

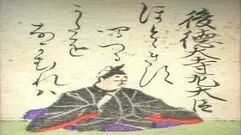
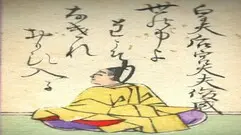
コメント