↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
76番 法性寺入道前関白太政大臣(ほっしょうじにゅうどうさきのかんぱくだいじょうだいじん) 『詞花集』
わたの原 漕ぎ出でて見れば 久かたの
雲居(くもい)にまがふ 沖つ白波
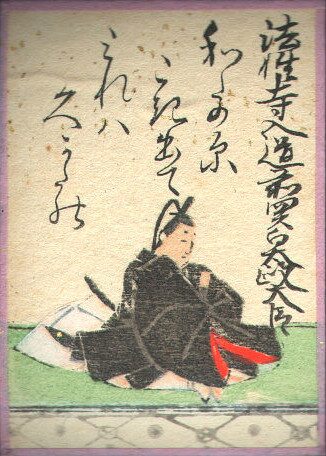
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
大海原に舟を漕ぎ出して眺めると、
はるか空の片隅にたなびく雲と見まがうように、沖の白波が立っているよ。
語句解説
【わたの原】
広々とした大海原のこと。
「わた」は海を意味します。
和歌ではしばしば「旅」や「別れ」を象徴する。
【漕ぎ出でて見れば】
舟を漕ぎ出して進むこと。
「漕ぐ(こぐ)」+「出づ」の連語になっています。
「見れば」= 上一段動詞「見る」の已然形 + 接続助詞「ば」で、順接の確定条件を表します。
【久かたの】
「雲居」に掛かる枕詞で、「天」「空」「光」などにもかかります。
意味は特にありませんが、語調を整える役割があります。
【雲居】
今回は雲そのものを意味します。
普段は空のことを指す古語です。
【まがふ】
「まちがえる、見分けがつかない、似ている」という意味。
今回は「白い波と白い雲の見分けがつかない」という意味です。
【沖つ白波(おきつしらなみ)】
沖の方に立つ白い波。
「沖つ」=「沖の~」という意味で、「つ」は格助詞です。
作者: 法性寺入道前関白太政大臣
藤原 忠通(ふじわらの ただみち)〈1097年 ~ 1164年〉
〈藤原忠通:Wikimedia Commons〉
平安後期を代表する摂関家の一人であり、藤原氏の中でも太政大臣に上り詰めた人物です。(太政大臣は天皇をも凌ぐ最高権力者)
父・藤原忠実のもとで育ち、後に摂政・関白を務め、朝廷の実権を掌握しました。
忠通の政治的キャリアは華々しいものでしたが、家庭内では深刻な対立もありました。
特に父・忠実とは対立し、弟の藤原頼長との確執は有名です。
この兄弟の不仲は保元の乱(1156年)の背景の一つともなり、忠通は後白河天皇側につき、弟・頼長は崇徳上皇側についたことで、藤原一族は大きく分裂しました。
↓白河天皇や保元の乱について解説しています、こちらもご覧ください!!↓
藤原忠通は政治の中枢にとどまり続け、藤原北家の権勢を維持します。
晩年には、嫡男である「九条兼実」に家督を譲り、九条家を創設する礎を築きました。
〈九条兼実:Wikimedia Commons〉
九条家は、のちの鎌倉時代にも摂政・関白を多数輩出する有力家系として続いていきます。
鑑賞:込み上げてくる不安、自然の光景から⛵
広大な海に舟を漕ぎ出したときの情景を詠んでおり、自然の雄大さと人間の小ささ、旅立ちの心細さや不安を感じさせる一首です。
視覚的な描写が非常に印象的で、海の沖に立つ白波が、遠く空にたなびく雲と見まがうという表現には、詠み手の繊細な観察眼と美的感覚が表れています。
海と空という境界の曖昧な広がりを重ねることで、現実と幻想の間に立つような、不思議な感覚を生み出しています。
また、この和歌には「旅」のモチーフが隠れており、舟を漕ぎ出すという行為は、日常を離れ未知の世界に足を踏み出すことの象徴とも解釈できます。
旅立ちに対する期待や不安、孤独感といった感情が、自然描写の中に巧みに織り込まれている点も見逃せません。
静かながらも深い感動を呼び起こす、古今和歌集らしい美しい一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた




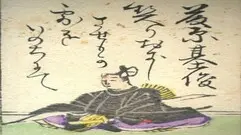

コメント