↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
74番 源俊頼朝臣(みなもとのとしよりあそん) 『千載集』
うかりける 人を初瀬(はつせ)の 山おろしよ
はげしかれとは 祈らぬものを
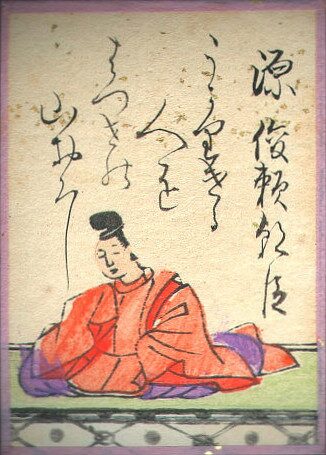
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
つれないあの人の心が変わるようにと、初瀬の観音様に祈ったけれど、
まさか、初瀬の山おろしがこんなにも激しく(=冷たくつらく)私自身に吹きつけてくるように祈ったわけではなかったのに。
語句解説
【うかりける人を】
「うし(憂し)」の連用形「うかり」+ 過去の助動詞「ける」
「憂し」=「思い通りにならない」とか「つれない」という意味。
【初瀬の山おろしよ】
「初瀬」= 奈良県桜井市にある長谷寺(下の写真)のある地。
〈画像:Wikimedia Commons〉
古くから観音信仰・恋愛成就の祈願所として知られます。
「山おろし」= 「山から吹き下りてくる激しい風」
【はげしかれとは】
形容詞「はげし(激し)」の命令形 + 願望の助動詞「かれ(=~なってほしい)」
「激しくあってほしい」という意味。
「とは」= そのまま「~とは」という意味。
【祈らぬものを】
「祈ったわけではないのに」の意味。
「ものを」は逆接の接続助詞。
相手の心が変わることを祈ったが、自分が苦しい思いをするようになる事までは望んでいなかったという、嘆きと皮肉が込められています。
作者: 源俊頼朝臣
源俊頼(みなもとの としより)〈1055年 ~ 1129年〉
平安時代後期の歌人・貴族で、三十六歌仙の一人でもある源経信(つねのぶ)の子です。
↓源経信の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓
父譲りの和歌の才に恵まれ、「歌の革新者」とも評される人物です。
白河天皇・堀河天皇・鳥羽天皇の三代に渡り仕え、「右中弁」などの官職に就きながら、宮廷文化の中心で活躍しました。
↓白河天皇を解説しています、こちらもご覧ください!!↓
彼の代表的な功績の1つが、勅撰和歌集『金葉和歌集(きんようわかしゅう)』の撰者となったことです。
この和歌集は、より感情表現を重視した新風の和歌が多く、伝統的な形式にとらわれない俊頼の個性が色濃く反映されています。
また、彼の私家集である『俊頼髄脳(としよりずいのう)』は、和歌の理論書としても注目される存在で、後の藤原俊成や藤原定家などにも影響を与えたとされています。
俊頼の歌風は、ときに風変わりで技巧的、ときに情熱的で人間味あふれたものも多く、保守派の中では異端視されることもありました。
しかしその斬新さと感情の濃さは、時代の転換期を象徴するものとして、高く評価されることも多いです。
鑑賞:観音様へのお祈り、虚しくも逆効果🗿
報われぬ恋に苦しむ心情を、奈良の霊場・初瀬の風景と重ねて詠んだものです。
「うかりける人」とは、冷たい態度を取る恋の相手を指しています。
「初瀬の山おろし」は、長谷寺のある険しい山地に吹き下ろす強く冷たい風で、ここでは自分の恋の苦しみを象徴する存在です。
そんな山おろしに向かって「これほど激しく吹け」とは決して祈っていないのに、まるで自分の心を荒らすように吹きつけてくると、嘆いているのです。
実際の祈願の場である長谷観音への参詣を恋の比喩に用いることで、宗教的な荘厳さと個人的な切実さが交錯した、深い情念が感じられる一首となっています。恋の苦しみが、自然の猛りと重なりあうことで、読む者の胸にも強く迫ってくる一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


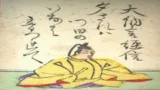

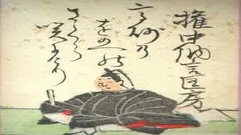
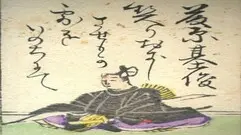
コメント