↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
6番 中納言家持(ちゅうなごんやかもち) 『新古今集』
かささぎの 渡せる橋に おく霜の
白きを見れば 夜(よ)ぞ更けにける
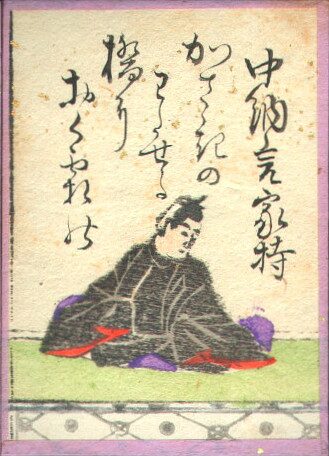
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
カササギが翼でかけたという天の橋(天の川のこと)に、
霜が白く降りているのを見ていると、夜もすっかり更けたものだと感じる
語句解説
【かささぎ(鵲)】
七夕伝説に登場する鳥。
織姫と彦星が年に一度天の川を渡るとき、翼を並べて橋をかけるという役目を持ちます。
〈かささぎ:Wikimedia Commons〉
この歌では、天の川にかかる幻想的な橋の象徴とされています。
【渡せる(わたせる)】
(橋などを)かけたという意味。
「渡す(かける・通す)」の連体形「渡せ」に、完了の助動詞「り」の連体形「る」がついたもの。
【おく霜】
「おく」は「置く」で、霜が地面や橋の上に降り積もっている様子。
〈霜:Wikimedia Commons〉
霜がうっすらと降りて白くなっている状態と表します。
【夜ぞ更けにける(よぞふけにける)】
「夜がすっかり更けてしまったのだなあ」の意味。
更け:動詞「更く(ふく)=時間が過ぎて夜が深くなる」の連用形。
にける:「ぬ(完了)」+「けり(詠嘆)」で、「すっかり〜してしまったなあ」という意味になる。
作者:中納言家持(大伴家持)
大伴 家持(おおともの やかもち)〈718年頃~785年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
本名を大伴家持(おおとものやかもち)と言い、聖武天皇に仕えた人物です。
↓聖武天皇について解説しているので、こちらもご覧ください!↓
大伴家持は高校で習う名前なので、こちらの名前の方が馴染みがあるかもしれません。
奈良時代を代表する歌人であり、また政治家としても活躍した人物です。
大伴氏という古代の名門豪族の出身で、朝廷に仕えながら多くの和歌を詠み、最終的には中納言という高位にまで昇進しました。(中納言は律令制度下の官職名)
大伴家持は、日本最古の和歌集『万葉集』の編纂に深く関わったとされており、自身の歌が470首以上も収録されていることからも、その重要性が伺えます。
彼の作風は自然や季節、人の感情を率直かつ写実的に表現するのが特徴です。
例えば「春の園 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つをとめ」といった色彩豊かな歌からも、その感性の豊かさが伝わります。(春の庭に紅く美しく咲く桃の花が、道を照らす様に咲き誇る中、その道に一人の乙女が立っている。)
政治の世界では藤原氏との政争に巻き込まれ、晩年には最終的に東国へ左遷され、波乱の生涯を終えました。
しかしその文学的功績は後世に大きな影響を与え、「万葉集の顔」とも言える存在として日本文学史に名を刻んでいます。
鑑賞:人冬の夜の静けさと、時間の移ろい ☃️
この歌は、冬の夜の静けさと、時間の移ろいを繊細に描いた一首です。
冒頭の「かささぎの渡せる橋」という表現は、七夕伝説に登場するカササギが天の川にかけた橋を指し、幻想的なイメージを呼び起こします。
実際の橋を意味しているとも、夜空にかかる天の川を例えているとも解釈でき、空想と現実が巧みに交錯している点に、この歌の大きな魅力が秘められています。
そこに「おく霜の白き」が重なり、霜が降りてあたりが白く染まる様子が目に浮かびます。
霜の白さはただの気候描写ではなく、静まり返った冬の夜を象徴しており、見る者の心に深い印象を与えます。
最後に「白きを見れば 夜ぞ更けにける」と結ばれる事で、視覚的な変化を時間の経過と共に描いています。
「音もなく更けていく冬の夜、その美しさと寂しさ」を、詩情豊かに詠み上げた、幻想的かつ写実的な歌なのです。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊





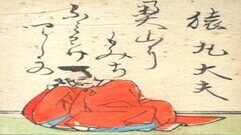
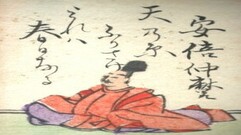
コメント