皆さんこんにちは!
今回は泰平の時代を築いた、江戸幕府の仕組みを解説していきます。
日本史史上3回目の幕府ですが、江戸幕府は全国を統治するのに、シンプルな仕組みを生み出しました。
人を統治する仕組みを江戸幕府から学んでいきましょう!
↓徳川家康が天下を取る過程を復習したい方は、こちらをご覧ください!!↓
江戸幕府の成立
〈1603年 徳川家康 征夷大将軍就任〉
1603年、「徳川家康」が「後陽成天皇」に「征夷大将軍」の宣下を受けました。

〈徳川家康:Wikimedia Commons〉
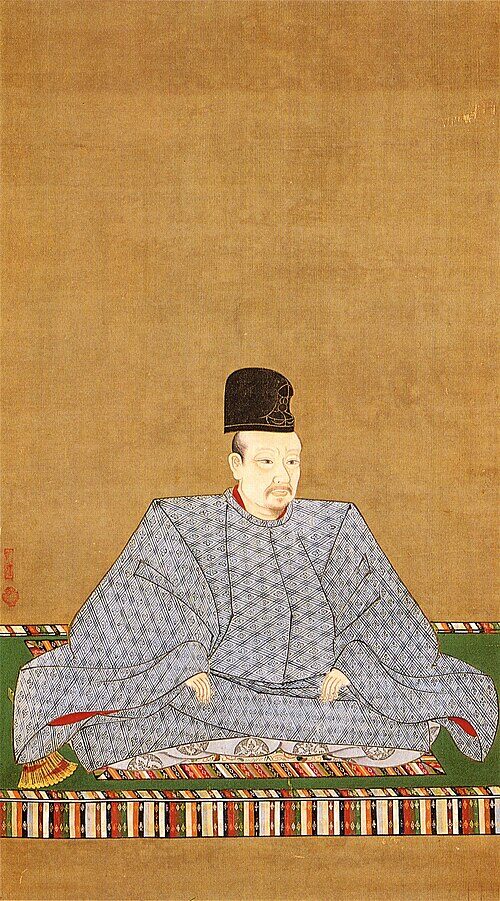
〈後陽成天皇:Wikimedia Commons〉
江戸に幕府を開き「江戸時代」が始まりました。

〈画像:Wikimedia Commons〉
大名の分類
江戸幕府は大名を3つのグループに分けていました。

親藩(しんぱん)
「親藩」には将軍の血筋が途絶えた時の保険の役割があります。
徳川家の親戚なので好待遇にしましたが、徳川家同士の争いを避ける為に権限は与えていません。
親藩に該当するのは、「松平家」や「徳川御三家(一橋・田安・水戸)」です。
譜代(ふだい)
「関ヶ原の戦い」以前から徳川家に仕えていた家臣が該当します。
信頼ある家臣なので、幕府の中枢で重要な役職に就く事が出来ました。
その代わりに小さい領土を与え、経済力を削ぎました。
有名なのは「井伊家」や「柳沢家」です。
外様(とざま)
「関ヶ原の戦い」以後に、徳川家に従った大名です。
大きな領地を持つ者が多いのが特徴です。
外様大名には大きな領地のを与える代わりに、「幕府の政治に口出し出来ないように幕府の役職に就けない」などの制限を加えました。
有名なのは「島津家」や「毛利家」です。
江戸幕府の支配構造
幕府は様々な仕組みを作ることで、全国の大名を管理しました。
「江戸幕府の将軍は全国の武士の頂点に立ち、全国の大名は将軍に従う立場」というのが、基本的な主従関係です。
「鎌倉時代の将軍と御家人の関係の様に、将軍が大名に土地の支配を認める代わりに、大名は将軍の為に働く」という、武士の基本を「徳川家康」は理解していました。
豊臣家の天下から徳川家の天下に移行する為には、土地支配の主導権を握る事が大切だと分かっていたのです。
江戸幕府の役職
江戸幕府には職種ごとに役職があり、政治や経済、裁判などを分担して行っていました。
基本的に幕府の役職には「譜代大名」しかなれません。
以下に具体的な役職を解説していきます。
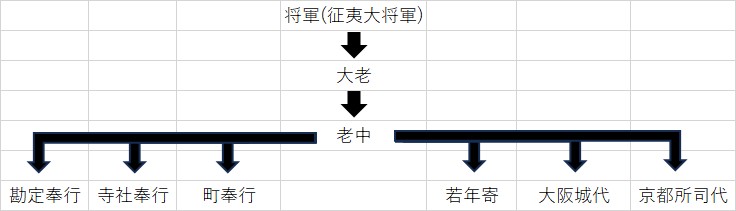
大老(たいろう)
臨時で置かれる最高の役職です。
大老が置かれる時は国が危機に直面している場合や、適任者がいる時です。
一番有名なのは「井伊直弼」です。
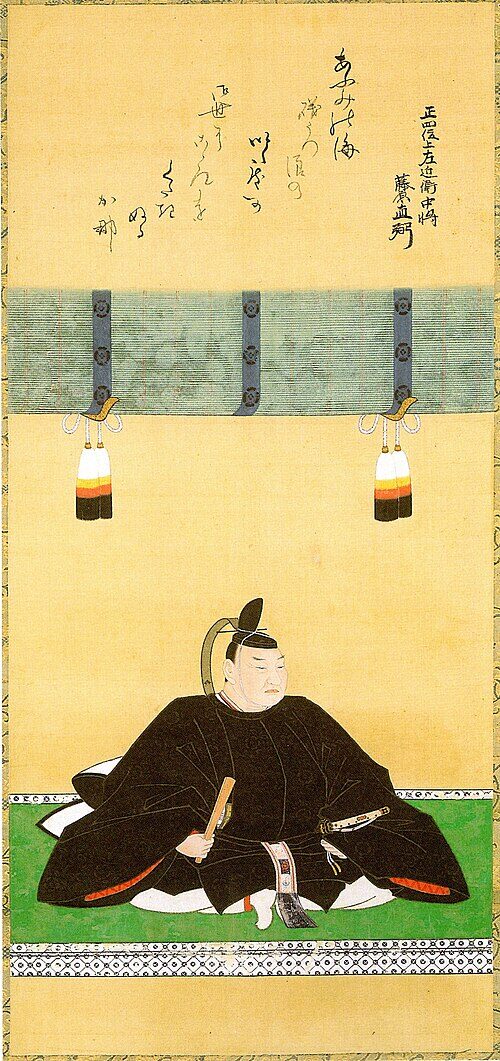
〈井伊直弼:Wikimedia Commons〉
老中(ろうじゅう)
普段の幕府で、一番上の役職です。
常時5名程度が、老中に選任されています。
1人にしていないのは、権力が集中しない様にする為です。
とは言っても、全員が同じ立場だと話合いが進まない場合もあります。
老中のトップである「老中首座」に、最終決定権があります。
「老中首座」で有名なのは、「田沼意次」や「阿部正弘」です。

〈田沼意次:Wikimedia Commons〉

〈阿部正弘:Wikimedia Commons〉
若年寄(わかどしより)
老中の補佐が主な仕事です。
旗本や御家人の監督も担当しています。
「老中」の「老」や「若年寄」の「年寄」は、戦国時代当初から徳川家の有力の家臣の事を、「老」・「年寄」と呼んでいた事に由来しています。
一番有名な人は「田沼意次」の息子である「田沼意知」です。
大阪城代(おおさかじょうだい)
大阪城の監視を担当します。

〈大坂城:Wikimedia Commons〉
「徳川家康」を幕府を開いた時、豊臣家はまだ存在しています。
豊臣家が勢力を高め、徳川家に反抗する動きを未然に防ぐ事が目的です。
豊臣家が大坂の陣で滅亡した後は、大阪の支配拠点として機能しました。
寺社奉行(じしゃぶぎょう)
この役職に「徳川家康」の支配センスを感じます。
「奈良時代では道鏡が皇位を狙う」、「戦国時代では一向一揆として大名に対抗する勢力に成長する」など、宗教を野放しにすると脅威になると理解していたのです。
全国の寺社を幕府の管理下に置く事で、反乱を未然に防止しました。
町奉行(まちぶぎょう)
江戸の市民生活や治安を守る、今で言えば警察と市役所を合わせたような役職です。
今も昔も、盗みや殺人などの事件は当然起こります。
街の治安が幕府の安定に直結する事も「徳川家康」は理解していました。
当時の人口の9割を占める農民の統制こそ、「税金の徴収」=「幕府の収入」に直結します。
「農民は生かさず殺さず」という言葉が残っている程です。
一番有名な人は「大塩平八郎」です。
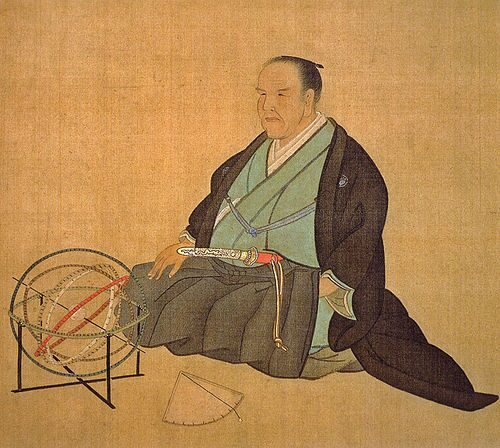
〈大塩平八郎:Wikimedia Commons〉
勘定奉行(かんじょうぶぎょう)
財政や税金などを管理する役職です。
現在で言う、「財務省」みたいなイメージです。
一番有名な人は、元禄小判を鋳造した「荻原重秀」です。
幕藩体制
幕府は全国を「直轄地(天領)」と「藩(はん)」に分けていました。
「天領」=「江戸幕府の直轄地」です。
「金山や銀山など資源が採れる所」や、「外様の有力な大名を監視できる所」に天領を設置し、反乱を防止していました。
天領以外は「藩」という、現在の都道府県の様に分かれていました。
それぞれの藩には独自の通貨発行権やルールの整備が認められており、半ば独立した小さな国として運営されていました。
幕府が全国の藩に地方の統治を任せる仕組みを「幕藩体制」と言います。
受験生の方へ
大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。
それが日本史一問一答です。
日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]
今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。
最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。
以下が実際の例題です。
日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、
[★★★]を唱える事によって救われると説いた。
文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。
例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。
私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。
学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。
自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。
早めに対策した者が受験勉強を制します。
さぁ、日本史を楽しみましょう!





コメント