↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
11番 参議篁(さんぎたかむら) 『古今集』
わたの原 八十島(やそしま)かけて 漕(こ)ぎ出でぬと
人には告げよ 海人(あま)の釣り舟
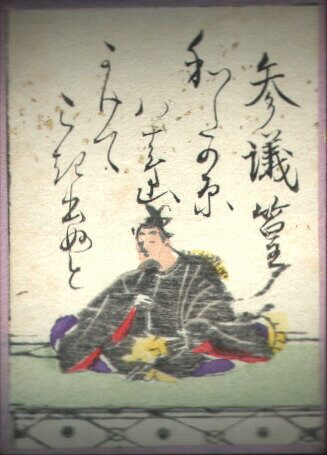
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
広い海原に、いくつもの島を目指して船出したと、
都にいる人に伝えてくれ。海人の釣り舟よ。
語句解説
【わたの原】
「海原(うなばら)」=広くて果てしない海のこと。
「わた」は「海」の古語。情景を雄大に表す。
【八十島(やそしま)】
「たくさんの島々」という意味。八十(やそ)は「多数」を表す言い回し。
特定の島ではなく、多くの島を指している。
【かけて】
「目指して」「向かって」の意味。
「〜に向かって動く」という方向性を表す語。
【漕ぎ出でぬ】
「漕ぎ出した」という意味。
「ぬ」は完了を表す助動詞「ぬ」の終止形。
【人には告げよ】
「都に残る人々には伝えてくれ」の意味。
「人」は都の人々を指していると解釈される。
【海人(あま)】
海に住む人、つまり漁師。特に小舟で漁をする人を指すことが多い。
【釣り舟】
魚を釣るための小さな舟。
旅立つ作者がその小舟を都への伝言を託す、象徴的な存在として使っている。
作者:参議篁(小野篁)
参議篁(さんぎたかむら)〈802年頃〜853年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
本名は小野篁(おのの たかむら)で、平安時代前期に活躍した学者・歌人・官僚です。
名門・小野氏の出身で、遣隋使として有名な小野妹子(下の写真)の子孫とも伝えられています。
〈画像:Wikimedia Commons〉
高校だと宇治拾遺物語の「小野篁、広才のこと」で習った方もいるかもしれません。
彼は漢詩・和歌・学問・書に秀でており、若くして朝廷で高官に就きました。
言葉の鋭さと反骨精神で知られ、時の権力にも臆せず発言する気骨のある人物でした。
その為、風刺的な歌や皮肉の利いた逸話も多く残されています。
中でも有名なのが、遣唐使の副使として中国に渡るよう命じられた際のエピソードです。
小野篁は航海を嫌ってあえて病を理由に出発を拒否し、結果として天皇の怒りを買い、隠岐の島に流されてしまいます。
この時の思いを詠んだのが、今回の歌である「わたの原 八十島かけて〜」だと伝えられています。
才能と独自の感性を武器に活躍した小野篁の姿勢は、現代でも自由な精神と知性を象徴する人物として、多くの人に親しまれています。
鑑賞:静かな諦念と人への思い 🌊
作者・小野篁が、都から遠く離れた隠岐の島へ流される際の心情を、詠んだものとされています。
広大な海に漕ぎ出すという場面を通じて、彼の旅立ちの決意や都に残る人々への思いが滲み出ています。
冒頭の「わたの原」という表現からは、果てしなく広がる海の光景が目に浮かび、孤独や不安、そしてそれを乗り越えようとする覚悟が感じられます。
「八十島かけて」という多くの島々を目指して進む様子には、単なる地理的な移動だけでなく、自らの運命に向かって船を進めるような意志の強さも込められています。
「人には告げよ 海人の釣り舟」という結びでは、ささやかな漁師の舟に、自分の思いを託して都の人々へ伝えてくれと語りかけています。
ここには、直接言葉で伝えられないもどかしさと、誰かに気持ちを届けてほしいという切実な願いが感じられます。
全体を通して、壮大な自然の描写の中に、作者の静かな諦念と、なお消えない人への思いが込められた一首です。
旅立ちの寂しさと誇りを、海と舟を通じて巧みに表現しており、読む者の心に深く残る作品です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊



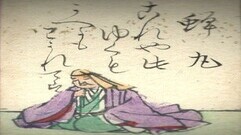
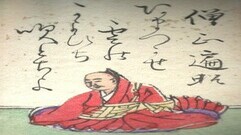
コメント