↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
88番 皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう) 『千載集』
難波(なには)江の 芦のかりねの ひとよゆゑ
みをつくしてや 恋ひわたるべき

〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
難波の入り江で刈り取った芦の根っこ(刈り根)の一節(ひとよ)ではないが、ほんの一夜の仮寝であったのに、
そのために私は身を尽くして、生涯想い続けることになるのだろうか。
語句解説
【難波江】
摂津国難波(現在の大阪府大阪市)の入り江。
芦が群生する低湿地として有名で、百人一首にも何首か取り上げられています。
【芦の】
「芦」= 水辺に生える植物で、和歌では秋の風物詩としても詠まれます。
〈画像:Wikimedia Commons〉
「芦」は今回出てくる「刈り根」、「一節」、「澪標(みおつくし)」と縁語です。
「難波江の芦の」までが序詞で、「かりねのひとよ」を呼び出します。
【かりねのひとよゆゑ】
「仮寝の一夜」= 一晩限りの男女の関係。
「刈り根の一節」= 葦を刈った根の1つ。
「芦を刈り取った根(刈り根)のひとよ(一節)」という意味と、「仮寝(旅先での仮の宿り)の一夜(ひとよ)」の掛詞になっています。
「ゆゑ(故)」= 理由・原因を表し、「~のために」という意味です。
【みをつくしてや】
「澪標(みをつくし)」= 難波の海に立てられた水路の標識。(下の写真)
〈画像:Wikimedia Common
身を滅ぼすほどに恋こがれる意味の「身を尽くし」と掛詞になっています。
「や」は疑問の係助詞で、後ろの「べき」と結んでいます。
↓澪標を使った和歌を他にも紹介しています、こちらもご覧ください!!↓
【恋ひわたるべき】
「恋ひわたる」= 「ずっと恋し続ける」という意味。
「べき」は推量の助動詞「べし」の連体形。
「みをつくしてや」の係助詞「や」の結びで、文末なのに連体形になっている事に注目です。
作者: 皇嘉門院別当
皇嘉門院別当(こうかもんいんのべっとう)〈生没年 不詳〉
平安時代後期に宮廷で活躍した女性歌人で、上流貴族の家柄に生まれたと考えられています。
後白河天皇の中宮である皇嘉門院藤原聖子に仕え、女房として宮廷生活を送りながら和歌の世界でも才能を発揮しました。
↓後白河天皇について解説しています、こちらもご覧ください!!↓
「別当」というのは宮中で特定の部署を取り仕切る役職名で、彼女の場合は皇嘉門院の女房としての官職名がそのまま呼び名として伝わっています。
勅撰和歌集にも選ばれており、掛詞や縁語を巧みに駆使する洗練された作風が評価されています。
生涯の詳細は多くが謎に包まれていますが、宮廷文化の中で才知と感性を兼ね備えた存在として記憶されているのです。
鑑賞:夜の刹那の時間、人生で身を尽くし🌌
時間の儚さと感情の持続という相反する要素を、巧みな言葉の選び方と構成で表現しています。
ごく短い出来事でありながら、それが心の奥深くまで染み込み、長く続く想いとなってしまう人間の心理が見て取れます。
作者が旅先で一夜限りの関係を持った時に詠んだ一首ですが、それほどに胸に焼き付いた夜だったのでしょう。
この歌の特徴は感情の激しさを直接的に訴えるのではなく、地名や風物を媒介として間接的に描き出しているところにあります。
そうすることで、表現は優美さを保ちつつ、内面の熱情を際立たせるという作者の見事な技巧が見て取れます。
また、現実の出来事と自然の光景が二重写しになり、短い一瞬と長い歳月の流れが一つの場面に収束している為、読者はその余韻を長く味わうことが出来ます。
平安後期の宮廷恋愛に見られる「秘めた情熱」や「抑制された表現美」がよく表れた作品です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた



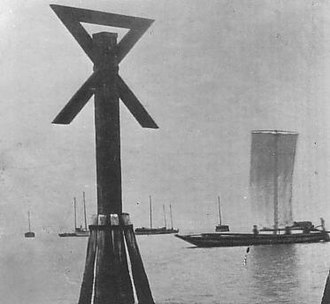
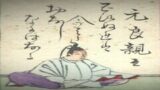

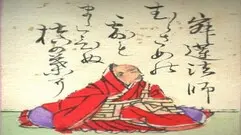
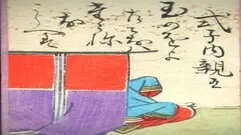
コメント