↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
81番 後徳大寺左大臣(ごとくだいじさだいじん) 『千載集』
ほととぎす 鳴きつる方を 眺むれば
ただ有明(ありあけ)の 月ぞ残れる
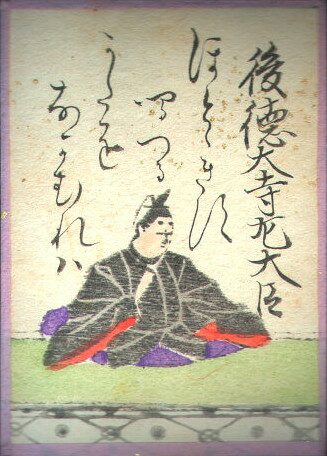
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
ほととぎすが鳴いた方を見つめると、ホトトギスの姿は見えず、
ただ有明の月だけが残っている。
語句解説
【ほととぎす】
夏を告げる鳥で、古来より和歌に多く詠まれています。
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代は初音(はつね=季節に初めて鳴く声)を聴く事が赴き深いとされ、ホトトギスは特に人気がありました。
【鳴きつる方を】
「つる」は完了の助動詞「つ」の連体形。
「方 」=方向、方角。
「ホトトギスが鳴いた方角」という意味。
【眺むれば】
「眺む」=「 物思いにふけって遠くを見る」の意味。
動詞「ながむ」の已然形 + 接続助詞「ば」で、順接の確定条件を表します。
【ただ有明の月ぞ残れる】
「ただ」= 他には何もなく、唯一。
「有明(ありあけ)の月」= 夜明けになってもまだ空に残っている月。
「る」= 存続の助動詞「り」の連体形で、強意の係助詞「ぞ」と係結びとなっています。
〈~ちょっと復習、係り結びの法則~〉
「ぞ」「なむ」「や(は)」「か(は)」= 結びの形が「連体形」に変化!
「こそ」= 結びの形が「已然形」に変化!
作者: 後徳大寺左大臣
徳大寺 実定(とくだいじ さねさだ) 〈1139年 ~ 1192年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した公卿であり歌人です。
父は徳大寺左大臣藤原公能(徳大寺公能)であり、父と区別するため後徳大寺左大臣と呼ばれています。
高い家格を背景に朝廷で重きをなし、左大臣などの要職を歴任しました。(左大臣は常職の中で最高位)
藤原俊成や藤原定家(作者の従兄弟)と同時代を生き、宮廷歌壇において優れた歌人として名を馳せます。
↓藤原俊成・藤原定家の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓
『新古今和歌集』には彼の繊細で情趣豊かな歌が多く収められ、後世にもその優美な作風が評価されました。
自然の景や四季の移ろいを通して心情を映し出す技巧に長け、情景描写の中にしっとりとした哀愁や余韻を漂わせる点が特徴です。
彼の人柄は温雅で上品と伝えられ、歌の世界でも品位と格調を重んじた作風が際立っています。
※「徳大寺」というのは地名由来の家名で、寺そのものと直接の宗教的関係は無いと言われています。
鑑賞:初夏を知らせるホトトギス、なんとかこの目に焼き付けたい🕊️
まだ夜の気配が空に残る夏の早朝に、ホトトギスが一声鳴き、その声に誘われて振り向いたとき、そこにはもうホトトギスの姿は無く、その代わりに淡く光を残す有明の月が空にかかっている、という静かで儚い情景を描いています。
この歌は、「暁聞郭公(あかつきにほととぎすをきく)」で詠まれた歌です。
平安時代の貴族たちにとって、ホトトギスはただの夏鳥ではありません。
三月から五月にかけて日本に渡ってくる彼らは、夏の訪れを告げる特別な存在で、「時鳥(ほととぎす)」「杜鵑(とけん)」など、呼び名を幾つも持ち、和歌の世界でも格調高い景物として愛されました。
特に、その年の「初音(はつね)」=「季節の訪れを告げる鳥の鳴き声」を聴くのは一大イベントで、貴族たちは初音を聴こうと夜通し起きて待ち、鳴き声がすればその方角を見るという風流な遊びを楽しんだのです。
気持ちは今で言う、初日の出みたいな感じですね。
ところがホトトギスは動きが速い為、鳴き声を追ってもその姿を目にすることはなかなか叶いません。
現代の私達からすれば「夜明け前に鳥の声を聴くために徹夜?」と、どこか不思議な話ですが、平安時代には自然と人の感情を密やかに結びつける、平安貴族の豊かな時間の使い方がありました。
この歌はそうした贅沢な文化の香りを、千年を越えて今に届けてくれるのです。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた



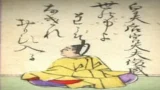

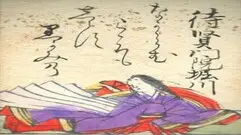
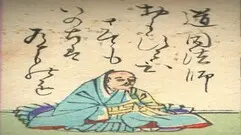
コメント