↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
79番 左京大夫顕輔(ふじわらの あきすけ) 『新古今集』
秋風に たなびく雲の 絶え間より
もれ出づる月の 影のさやけさ
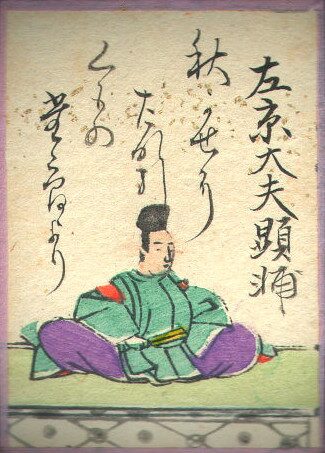
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
秋風にたなびく雲の切れ間から、
もれて差し出る月の光が、なんと清らかで澄みきっていることよ。
語句解説
【秋風にたなびく】
「秋風」= 秋に吹く風で、涼しさや澄んだ空気を感じさせる季語。
「に」は原因を示す格助詞。
「たなびく」= 雲や煙などが横に長く漂うこと。
【雲の絶え間より】
「絶え間」は途切れた部分、切れ目のこと。
ここでは雲の切れ目を指す。
「より」は起点を表す格助詞。
【もれ出づる】
動詞「もれ出づる」は「もれ出づ」の連体形。
「もれ出づる」= 隙間から外に出てくること。
ここでは月の光が雲間から漏れる様子。
【月の影のさやけさ】
「月の影」= 月の光。
古典では「影」は光の意味を持つ。
「さやけさ」= 形容詞「さやけし」を名詞化したものです。
「清らかで澄みきっていること」「音や光、空気などが明瞭で美しいさま」を表します。
作者: 左京大夫顕輔
藤原顕輔(ふじわらの あきすけ) 〈1090年 ~ 1155年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代後期の公家であり歌人で、父は藤原顕季(けんすえ)です。
六条藤家と呼ばれる歌人の家系に生まれ、藤原俊成や西行とも交流を持ちました。
↓藤原俊成や西行の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓
歌風は洗練された優美さと、自然描写の巧みさに定評があり、『詞花和歌集』や『金葉和歌集』など複数の勅撰和歌集に作品が収められています。
また、自らも歌集の編纂や和歌の選定に関わった人物です。
官職としては左京大夫(都の東半分を管轄する役職)に任じられたことから、この官職名で呼ばれることが多くなりました。
晩年まで歌壇で影響力を持ち、宮廷文化の発展にも寄与しました。
彼の和歌は、当時の貴族社会が求めた上品で繊細な美意識をよく体現しています。
鑑賞:秋の風物詩、心のままに🌕
秋の澄んだ空気と月の光を、雲の動きとともに鮮やかに切り取った情景詩です。
秋風に流される雲がたなびき、その切れ間から月明かりがもれる瞬間を「さやけさ」という一語で締め括っています。
視覚的な美しさだけでなく、心に染み入る静けさと清涼感が際立っています。
注目すべきは、自然の移ろいそのものに美を見出している点です。
雲が月を隠しまた現れるという一瞬の変化が、秋の夜らしい移ろいと儚さを象徴しています。
光と影の対比、静と動の調和が巧みに表現され、読む者に清らかな余韻を残します。
〈~理解が深まる、この歌の背景!~〉
この歌は崇徳院に捧げられた百首歌「久安百首」で、藤原顕輔が披露したものです。
「百首歌」は与えられたお題に沿って詠んだ歌(題詠)を100首集めたもので、百人一首77番の崇徳院の歌も、「百首歌」から採られています。
↓崇徳院の和歌も解説しています、こちらもご覧ください!!↓
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


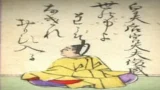
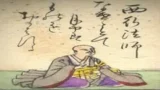

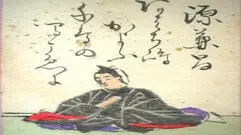
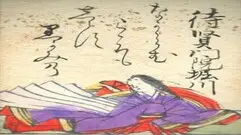
コメント