↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
7番 安倍仲麿(あべのなかまろ) 『古今集』
天(あま)の原 ふりさけ見れば 春日なる
三笠(みかさ)の山に 出(い)でし月かも

〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
広々とした夜空を仰いで見上げると、故郷・春日の三笠山から昇っていた、
あの懐かしい月が、今ここにも昇っているのだなあ。
語句解説
【天の原】
「果てしなく広がる大空」という意味。
「原」は「広がる場所」のイメージで、「天の原」で「どこまでも広がる空」という雄大な景色を表現しています。
【ふりさけ見れば】
「遠くを仰いで見れば」という意味。
「ふりさける」は「上の方を見渡す」という古語表現。
【春日なる三笠の山】
奈良の春日大社の近くにある三笠山。
〈画像:Wikimedia Commons〉
万葉集や古典でよく詠まれる場所なので、覚えておきましょう!
【出でし月かも】
「かつてその山から昇った月なのだなあ」
「出づ(いづ)」の連用形「出で」+過去の助動詞「き」の連体形「し」。
「かつて昇った月」の意味となります。
作者:安倍仲麿(阿倍仲麻呂)
阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)〈718年頃~785年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
阿倍仲麻呂(あべのなかまろ)は、奈良時代に活躍した国際的な学者・政治家・歌人であり、日本人として初めて唐の朝廷に仕えた人物として知られています。
貴族の名門・阿倍氏に生まれた仲麻呂は、幼い頃から学問の才に優れ、16歳の時に遣唐使の一員として中国へと渡っています。
↓遣唐使について解説しているので、こちらもご覧ください!↓
唐の都・長安では、当時の最先端の知識や制度を学び、現地の役人登用試験である科挙にも合格しました。
唐の皇帝からも重用され、「晁衡(ちょうこう)」という名を与えられて、高官として活躍しています。
753年に、あの有名な鑑真と共に日本への帰国船に乗りましたが、暴風に遭って航路を外れ、ベトナム近くの安南(あんなん)に漂着してしまったと言われています。
この遭難によって、仲麻呂はやむを得ず唐の都・長安に戻る事になりました。
以後も何度か帰国を試みましたが、唐の帝から重宝されていて中々返して貰えず、最終的に日本の土を踏むこと無く、中国でその生涯を終える事になりました。
鑑賞:望郷の念と叶わぬ希望 🌙
阿倍仲麻呂の望郷の念とがしみじみと滲む名歌です。
広大な夜空を見上げたとき、かつて自分が日本の奈良・春日の三笠山から見た月が、今まさに遠い異国の地・唐(中国)の空にも昇っている事に気づき、そこに深い感慨を抱いた心情が率直に詠まれています。
この歌の美しさは、「月」という自然の象徴を用いて、時間と空間を超えた故郷との繋がりを感じている点にあります。
同じ月を見ているという事実が、言葉や距離を超えて心を通わせる手がかりとなり、作者はその月に故郷の面影を重ねているのです。
月は変わらずに空を巡る存在であるからこそ、それを見上げる旅に懐かしい記憶が蘇り、故郷を離れて生きる者の孤独や切なさが一層深く感じられます。
また、「かも」という詠嘆(感動や気づき)を表す終助詞によって、思いがふとこぼれ出るような余韻が生まれており、言葉にしきれない感情の揺らぎも見えてきます。
この一首は、普遍的な人の心のありようを映し出しています。
故郷を離れて生きる人、過去を懐かしむ人、空を見上げて想いを馳せる人——そうした誰もの心に通じる、優しくも切ない余韻を残す和歌なのです。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊

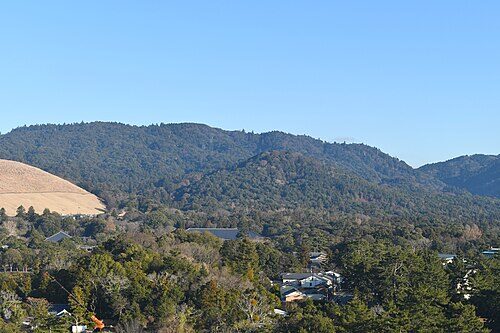
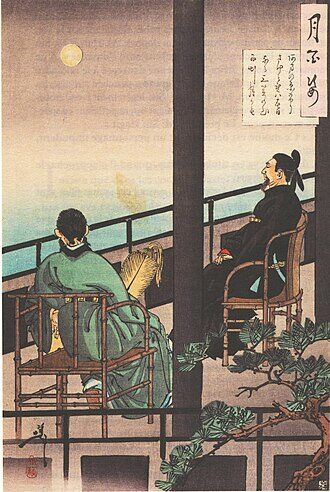

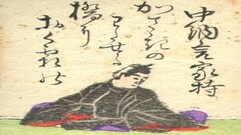
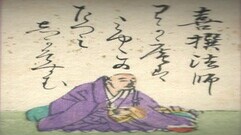
コメント