↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
62番 清少納言(せいしょうなごん) 『金葉集』
夜をこめて 鳥の空音(そらね)は 謀(はか)るとも
よに逢坂(あふさか)の 関は許さじ

〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
夜が明けぬうちに、鶏の鳴きまねをしてだまそうとしても、
決して逢坂の関所は通しはしませんよ。
語句解説
【夜をこめて】
動詞「こむ」の連用形「こめ」は、「しまい込む」とか「包みこむ」などの意味で使われます。
今回は「まだ夜のうちに」という意味です。
【鳥の空音(そらね)】
「空音」=「鳴き真似」の事を指します。
特に「鶏の鳴きまね」を指し、夜明けを騙す為に、人が真似した鳴き声の事を指しています。
【謀(はか)るとも】
「騙そうとしても」、「策略をめぐらしても」という意味。
「とも」= 逆接の接続助詞で、「~しても」という意味です。
「鶏の鳴き真似の謀ごと」は、中国の史記の中のエピソードや伊勢物語をモチーフにしたと考えられています。
【よに逢坂(あふさか)の関は許さじ】
「よに」= 「まったく、決して」、強い否定を表す副詞。
「逢坂(あふさか)の関」= 山城国(京都)と近江国(滋賀)の境にあった関所。(下の写真は、和歌によく出てくる3つの関所)
〈画像:Wikimedia Commons〉
「逢坂の関」は男女が夜に逢って過ごす「逢ふ」と意味を掛けた掛詞にもなっています。
「許さじ」= 許さないという意味で、「じ」は打消しの意志(〜まい)の助動詞。
全体で、「逢坂の関を通るのは許さない」という意味と、「貴方が逢いに来るのは許さない」という意味が掛けられています。
作者: 清少納言
清少納言(せいしょうなごん) 〈966年 ~ 1025年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
父は著名な歌人・清原元輔であり、彼女の本名は分かっていません。
↓清原元輔の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!!↓
平安時代中期に活躍した才女であり、随筆文学の金字塔『枕草子』の作者として特に名高い人物です。
宮中での生活や季節の美、日常の出来事、人々への鋭い観察などを自由な筆致で書き綴った『枕草子』は、千年以上を経た現在も多くの人々に読み継がれています。
その文体には、明快さ、感受性、知性、そしてユーモアが満ちており、彼女の個性や価値観が強く反映されています。
政治面では、中宮・定子に女房(=宮廷に仕える女性)として出仕した事からも、周囲が彼女の実力を認めていた事が分かります。
和歌や漢詩、物語などにも通じた教養ある女性であり、宮廷サロン文化の中心で輝いた人物です。
鑑賞:男の謀、彼女には通用しない🐓
清少納言らしい、ユーモアと知性を感じさせる一首です。
注目すべきは、物語文学の中でも知られている「鶏の鳴きまねで関所を通る」という機転の利いた逸話です。
『伊勢物語』の主人公が鶏の声を真似て夜明けを装い、関守をだまして逢瀬を果たす場面を、あえて逆手にとった表現を和歌に反映させています。
後半では、相手がどんなに巧妙に企んでも、私は決してその手には乗らない、という毅然とした態度が表れています。
「よに許さじ(決して許さない)」という言葉は、理知的な女性の意志表明であり、恋の駆け引きにおいても軽々しく心を許さない自負や慎みを表しています。
また、「逢坂の関」は実在の地名であると同時に、「逢う」を連想させる語でもあり、地名と恋の関係を掛詞的に使う技巧も注目に値します。
古典的教養と批評性、そして女性の知的な自己表現が融合した傑作です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


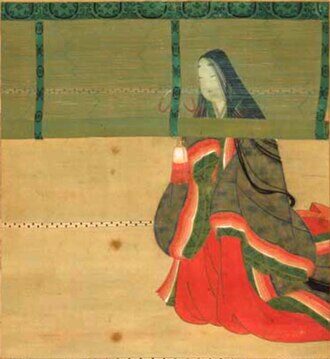
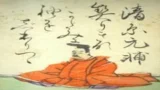
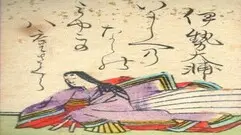
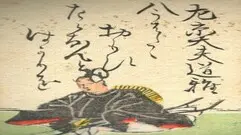
コメント