↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
55番 大納言公任(だいなごんきんとう) 『千載集』
滝の音は 絶えて久しく なりぬれど
名こそ流れて なほ聞こえけれ
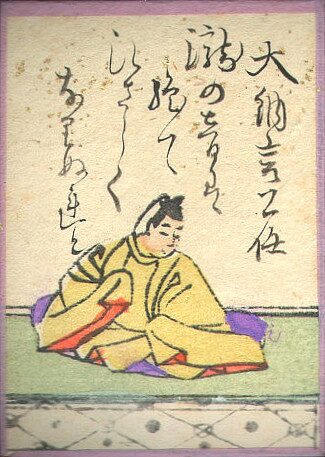
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
滝の音は、もうとっくに絶えてしまって久しいけれど、
その名(評判・名声)は今でも世に伝わって、なお聞こえてくるものだ。
語句解説
【滝の音は】
滝が流れ落ちる音。
「滝」は比喩的に、人やものの勢い・名声・存在感を象徴することもある。
【絶えて久しくなりぬれど】
「絶えて」=動詞「絶ゆ(たゆ)」の連用形+接続助詞「て」。
「絶える」は「途絶える」「止まる」という意味。
「にけり」= 形容詞「久し(ひさし)」の連用形で、「長い間」の意味。
動詞「なる(〜になる)」+完了の助動詞「ぬ(完了)」の已然形「ぬれ」+逆接の接続助詞「ど」。
「〜になってしまったけれども」という意味。
【名こそ】
「名」は名声や評判のこと。
「こそ」は強調の係助詞です。
係り結びの文法で、結びに已然形(聞こえ「けれ」)が来る。
【流れて】
動詞「流る(ながる)」の連用形で、「流れる」「世間に広まる」などの意。
「流れ」は滝の縁語です。
【なほ聞こえけれ】
「なほ」は「それでもやはり」の意味の副詞です。
動詞「聞こゆ(きこゆ)」の已然形+過去の助動詞「けり」の已然形「けれ」。
「けれ」は、前の「こそ」を結ぶ言葉で「けり」の已然形となります。
作者: 大納言公任
藤原公任(ふじわらのきんとう) 〈966年 ~ 1041年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代中期の貴族・歌人・学者であり、当時の文化人の中心的存在でした。
父は関白・藤原頼忠(よりただ)、藤原氏の中でも名門中の名門に生まれ、政治と文化の両面で活躍しました。
彼は特に文学と和歌の分野で高い評価を受けており、『三舟の才(さんしゅうのさい)』(和歌・漢詩・管弦すべてに優れていた人物)として後世に知られています。
また、和歌に関する重要な歌論書である『和漢朗詠集(わかんろうえいしゅう)』を編んだことでも有名です。
洗練された言葉選びと理知的な構成が特徴で、宮廷文化の成熟を象徴する存在です。
自然の描写を通して人の心情を詠む手法にも優れ、まさに「教養と感性を兼ね備えた貴族詩人」と言えるでしょう。
彼の作品は『拾遺和歌集』や『後拾遺和歌集』など、多くの勅撰集に収められており、百人一首にもこの滝の歌が採られています。
鑑賞:かつての音、今はもうなくても 💦
過ぎ去ったものの存在感が、なお世の中に残り続ける不思議さと余韻を、美しく表現した一首です。
滝の音が既に絶えて久しい、つまりその姿も音も現実にはもうなくなってしまった。
しかし、その「滝の名」はいまだに人々の間で語り継がれている。
視覚にも聴覚にも届かないのに、言葉や記憶によって存在し続けているものがある、という事を詠んでいます。
かつては激しく流れていた滝もやがて水が枯れ、静けさに包まれるように、人の栄華や存在もやがて形を失っていく。
それでも名声や評判は「流れるように」世に残り、静かに人々の耳に届いていくのです。
藤原公任は、目に見える現象の背後にある「名の力」「記憶の重み」に着目し、それを簡潔な言葉で巧みに表現しています。
この歌には、自然と人生、名と存在、音と記憶という対比が織り込まれており、知的で深い余情を湛えた作品です。
また、「滝」という対象に対して「音」「流れ」「名」といった要素を関連づけることで、読み手に見えないものの存在感を強く意識させるところにも、この歌の優れた詩的技術が表れています。
静けさの中に、かえって深い響きを感じさせる、洗練された和歌です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた



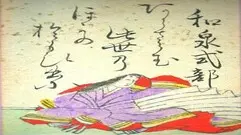
コメント