↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
53番 右大将道綱母(うだいしょうみちつなのはは) 『拾遺集』
歎きつつ ひとり寝(ぬ)る夜の 明くる間は
いかに久しき ものとかは知る
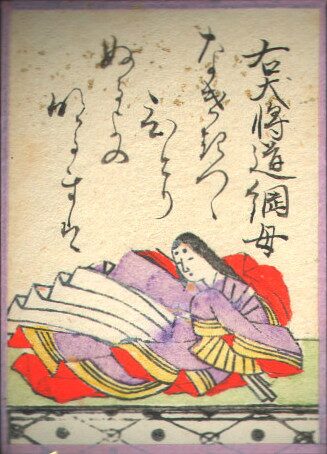
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
嘆きながら一人で寝る夜が明けるまでの時間が、
どれほど長く感じられるものか、あなたにはきっとわからないでしょう。
語句解説
【歎きつつ(なげきつつ)】
「歎く(悲しむ、つらく思う)」の連用形。
「つつ」は動作や作用の反復(繰り返し)を表す接続助詞。
【ひとり寝る夜の】
「寝る」=動詞「寝(ぬ)」の連体形。
当時は男性が女性の家に夜中に通う習慣がありました。
作者は女性なので、夫が自分の家に訪れず、一人寂しく寝るという意味です。
【明くる間は】
「夜が明けるまでの間は」という意味。
「明くる」= 動詞「明く」の連体形。
【いかに久しきものとかは知る】
「いかに」=「どれほど」「どのように」など、程度や様子をたずねる副詞。
今回は「どんなに~だろうか」と問いかける言い方になっています。
「久しき」= 形容詞「久し」の連体形で、「長く感じる」という意味。
「かは」は反語表現の係助詞で、「〜など(わかるはずがない)」のような意味を含みます。
「知る」=動詞「知る」の連体形で、「かは」と係り結びの関係になっています。
作者: 右大将道綱母(藤原道綱母)
藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)〈936年 ~ 995年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代中期の女性で、別名は藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)です。
本名は分かっていません。
「蜻蛉日記(かげろうにっき)」の作者として知られ、自身の心情や日常を綴ったその日記文学は、後の文学にも大きな影響を与えました。
藤原兼家(ふじわらのかねいえ)との間に藤原道綱(みちつな)という子をもうけますが、正妻ではなく側室という立場でした。
藤原兼家の関心が他の女性に向いた事により、孤独や不安、愛されない苦しみを感じるようになり、それが「蜻蛉日記」の随所に表れています。
自立した視点で感情を言葉にしていくその筆致は、当時の女性の内面を生々しく伝えており、女性文学の先駆けとも言える存在です。
彼女の書いた作品は、貴族社会における女性の生きづらさや、家庭内の地位、恋愛関係の現実などを描いており、その内容は現代にも通じる共感を呼び起こします。
日記文学を通して、平安女性の心の声を私たちに届けてくれる、非常に貴重な文学者の一人です。
鑑賞:一人寂しく待つ夜、貴方には分からない🌙
孤独な夜のつらさと、それを誰にも理解して貰えない寂しさを訴えている一首です。
作者は嘆きながら一人で過ごす夜の長さを身にしみて感じており、その時間がどれほど苦しく長く感じられるものかを、この和歌に込めています。
「歎きつつ」「ひとり寝ぬる」「明くる間は」といった言葉の流れにより、夜の長さと孤独が広がっていくような感覚があります。
「いかに久しきものとかは知る」という結びでは、その孤独を誰にも理解してもらえない切なさが反語で表現され、心の奥に残る余韻を生み出しています。
旦那に対して「分かってもらえない女性の苦しみ」を非常に繊細に表しており、千年以上たった現代でも共感を呼ぶ力を持っています。
静かな語り口の中に、深い感情の波が隠されている、味わい深い一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


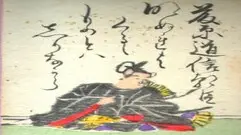
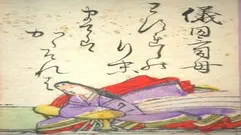
コメント