↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
47番 恵慶法師(えぎょうほうし) 『拾遺集』
八重葎(やへむぐら) しげれる宿の さびしきに
人こそ見えね 秋は来にけり
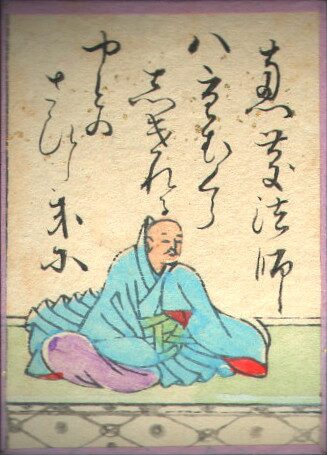
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
幾重にもむぐら(雑草)が生い茂っている、この荒れ果てた家の寂しさの中に、
人の姿こそ見えないけれど、秋だけは確かにやって来たのだなあ。
語句解説
【八重葎(やえむぐら)】(下の写真)
〈画像:Wikimedia Commons〉
「葎(むぐら)」はツル状の雑草のこと。
家や庭が荒れた場所によく生い茂る草。
「八重」は「幾重にも重なって」という意味で、雑草が深く茂っている様子を強調しています。
【しげれる宿】
動詞「茂る」の連用形+完了の助動詞「れる」。
「生い茂っている」「びっしりと草が生えている」という状態。
「宿」=「住まい」「家」のこと。
ここでは、今は人が住まなくなった寂しく荒れた住居を指しています。
【さびしきに】
「さびしき」は形容詞「さびし(寂し)」の連体形。
「に」は格助詞で、「~の中に」「~において」という意味。
全体で、「寂しさの中に」「寂しいその様子に」という意味。
【人こそ見えね】
「人の姿は見えない」という意味。
「ね」は、打ち消しの助動詞「ず」の已然形。
「こそ〜ね」は強調の係り結び(係助詞「こそ」と已然形「見えね」)。
【秋は来にけり】
「秋が来てしまった」という意味。
「に」は完了の助動詞、「けり」は過去・詠嘆の助動詞。
「確かに秋が来たのだなあ」という感情を込めています。
作者: 恵慶法師
恵慶法師(えぎょうほうし)〈生没年 不詳〉
平安時代中期に活躍した歌僧です。
『拾遺和歌集』を筆頭に複数の勅撰和歌集に作品が収録されており、当時から歌人として高い評価を受けていたことが伺えます。
「法師」という呼称が示す通り、彼は出家して僧となった人物で、俗世から離れた立場で自然や人生の移ろいを見つめていたと考えられます。
しみじみとした感情や、季節の変化に寄せる繊細な感受性が特徴であり、物事の奥にある静かな哀しみや、世の無常を感じ取る鋭さに長けていました。
自然や人の気配を通して、目には見えない感情や時間の流れを描き出す表現力に優れており、同時代の他の歌人達とは一線を画す独自の世界観を持っていたといえます。
鑑賞:変わらず訪れる秋、人の気配は無くなっても🌿
人が住まなくなり草が生い茂った寂しい住まいに、ひっそりと訪れる秋の気配を描いています。
表面上はただの風景描写のように見えますが、その背後には人の営みが消えた後の静けさや、時の移ろいへの深い感慨が込められています。
特に印象的なのは、「人こそ見えね」という言い回しです。
人の不在を強調する事で、かつての賑わいが失われた事への寂しさや、空間に満ちた「無」の感覚を際立たせています。
そして、「秋は来にけり」と続き、寂しさの中にも確かに季節が巡っているという、時の流れの確かさや自然の律動が感じられます。
秋という季節は、古来、人生のはかなさやもののあはれを感じさせる象徴とされてきました。
この歌でも目には見えない時間の経過や、過ぎ去った日々の余韻が、秋の訪れとともに静かに浮かび上がってきます。
単なる自然描写に留まらず、人の不在や変わってしまった時代の空気までも含めて詠み込んだ、深い余韻を持つ一首です。
寂しさと共にどこか温かな、自然との一体感のようなものを、読み手の心にも残してくれます。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


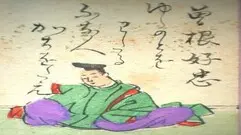
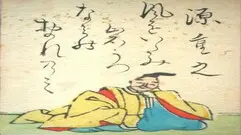
コメント