↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
46番 曽禰 好忠(そねのよしただ) 『新古今集』
由良の門(と)を 渡る舟人(ふなびと) かぢをたえ
ゆくへも知らぬ 恋の道かな
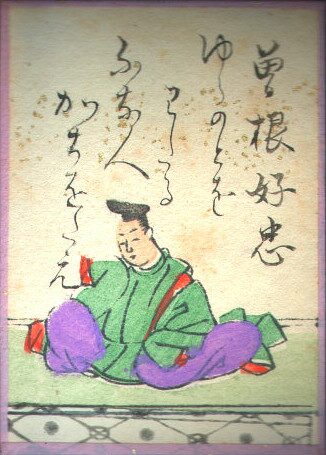
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
由良の海峡を渡る舟人が、櫂(かい)を失って行く先も分からなくなるように、
これからどうなるか分からない、どう進んでいいのかも分からない私の恋も道だ。
語句解説
【由良の門(と)】(下の写真の青い線が由良川)
「由良」は現在の京都府と兵庫県の境にある海峡(下の写真は由良川の道)。
〈画像:Wikimedia Commons〉
「門(と)」は「海峡」や「水路の入口」の意。
つまり「由良の海峡」。
【渡る舟人(ふなびと)】
「渡る」=「(海や川などを)わたる」。
ここでは舟人が由良の海を航行している様子。
「舟人」= 船を操る人、船乗り。
恋に例えている主人公自身が、舟人の姿に重ねています。
【かぢをたえ】
「かぢ」は、櫓(ろ)や櫂(かい)のように舟を操る道具のこと。
↑分かりやすい画像があったので、確認してみて下さい!↑
船の方向を変える現在の「舵(かじ)」とは異なります。
「たえ」= 下二段活用動詞「絶ゆ」の連用形。
「なくなる」という意味で、ここまでが序詞です。
【ゆくへも知らぬ】
上の句の流される舟の行き先と、下の恋の道に迷う部分との両方を意味します。
「知らぬ」= 動詞「知る」の未然形+打消しの助動詞「ぬ」。
「わからない」「見当がつかない」という意味になります。
【恋の道かな】
「道」はこれからの恋の成り行きを意味します。
「門(と)」や「渡る」「舟人」「かぢ」「行くへ」「道」はすべて縁語です。
「たえ」= 詠嘆・感嘆を表し、「〜だなあ」「〜ことよ」の意味です。
作者: 曽禰好忠
曽禰好忠(そねのよしただ)〈生没年 不詳〉
平安時代中期の歌人で、姓からも分かるように「曾禰氏(そねし)」という古代氏族の出身です。
『後撰和歌集』『拾遺和歌集』などの勅撰和歌集に作品が収められており、私家集として『曾禰好忠集』を遺しています。
その歌風は、技巧的でありながらも感情の表現に鋭く、時には風刺的で独自性の強い内容を詠んだことから、「異色の歌人」とも称されます。
偏狭な性格で自尊心が高かったことから、社交界に受け入れられず孤立した存在ではありました。
しかし、新奇な題材や『万葉集』の古語を用いて斬新な和歌を読み、平安時代後期の革新歌人から再評価されました。
文才と感性に優れた人物で、平安中期の和歌の多様性を象徴する歌人の一人と言えるでしょう。
鑑賞:不透明な恋の道、制御できない舟のように🚣♂️
恋の不安と迷いを、自然の情景に巧みに例えた一首です。
「由良の門(と)」とは海の流れが速く、通過が難しい海峡のことであり、古来より航行の難所とされていました。
その由良を渡る舟人が「かぢ」を失うという描写は、まさに制御を失って漂う状態を象徴しており、ここに恋の行く末が見えない心情が重ねられています。
「恋の道」という表現によって、恋愛が一つの進むべき道として捉えられており、その道の先がどうなるのか分からず、どう舵取りすればよいのかさえも分からない、という深い戸惑いや不安が伝わってきます。
この歌の魅力は、情景描写と心情表現が完全に一致している点にあります。
激しい潮の流れに流される舟と、激しい感情に翻弄される心。
その両方を、「かぢをたえ」という一言で結びつけ、恋という普遍的なテーマを具体的かつ象徴的に描き出しています。
感情の起伏を抑えながらも、内面の不安定さがじわりと滲み出るような構成になっており、読む人に深い共感と余韻を残す一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


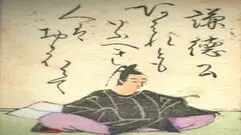
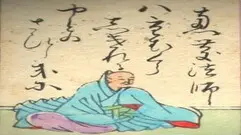
コメント