↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
43番 権中納言敦忠(ごんちゅうなごんあつただ) 『拾遺集』
逢ひ見ての のちの心に くらぶれば
昔はものを 思はざりけり
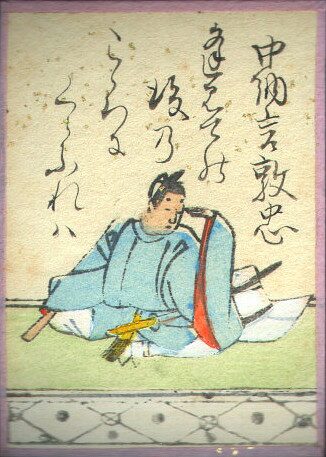
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
恋しい人とついに逢瀬を遂げてみた後の恋しい気持ちに比べたら、
逢う前に抱いていた恋の悩みなど、悩みとも言えないものだったのだなぁ
語句解説
【逢ひ見て(あひみて)】
「逢ふ」は男女が契りを交わすこと、「見る」も同じような意味。
合わせて「男女が関係を持つ」という意味になる。
【のちのこころ】
「逢った後の気持ち、心情」を指す。
逢瀬の後に生じた深い思いを表す。
【くらぶれば】
「比べると」の意味。
動詞「くらぶ」の已然形に接続助詞「ば」が付き、順接の確定条件を表します。
【昔は】
「昔」=「かつては」「以前は」の意味。
ここでは、逢う前のことを指す。
【ものを思はざりけり】
「ものを思ふ」は好きな人の、恋のもの想いをする意味です。
「ざり」は打消の助動詞の連用形で、「けり」は詠嘆の助動詞。
「昔は」と合わせて、「逢瀬を遂げる前の恋心なんて軽いものだったんだなぁ」という気づきを表しています。
作者: 権中納言敦忠
藤原 敦忠(ふじわらのあつただ)〈906年 ~ 943年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代中期の貴族・歌人で、本名は藤原敦忠と言います。
和歌の才能に優れ、三十六歌仙の一人に数えられています。
『拾遺和歌集』や『後撰和歌集』など、複数の勅撰和歌集に彼の歌が収められており、文化人としての足跡を現代に伝えています。
藤原敦忠は藤原道長の時代よりも少し前に活躍した人物で、貴族社会における恋愛や交流の一端を垣間見ることができる存在です。
彼自身の人物像は史料が少なく、詳細は不明な点も多いものの、平安時代の文化や感性を体現した人物の一人として、後世に名を残しています。
鑑賞:気づいた恋の悩み、成就した先に😔
恋愛における心の移ろいと、その深まりの驚きを率直に表現した和歌です。
過去の恋と現在の恋とを比較し、「あの頃は何も思っていなかった」と回顧するように、今抱える想いの強さに、自身さえ驚いている様子が読み取れます。
「逢ひ見てののちの心」は、恋人と実際に逢って関係を持ったあとの心の動きを指しています。
それまでの自分の感情は、今と比べればまるで「思っていなかった」に等しいという、強烈なコントラストを描いています。
つまり、恋が成就したことで逆に苦しみや執着が生まれ、恋の本当の重さを知ったという感覚です。
「恋が成就したことで逆に苦しみや執着が生まれた」といった感覚は、藤原敦忠が自らの恋愛経験を通じて心の奥底で感じていたことを、静かに表現したものかもしれません。
恋愛が進展する事で、感情はむしろ複雑さを増していく。
その人間心理の変化を的確に捉えた、非常に余韻深い一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

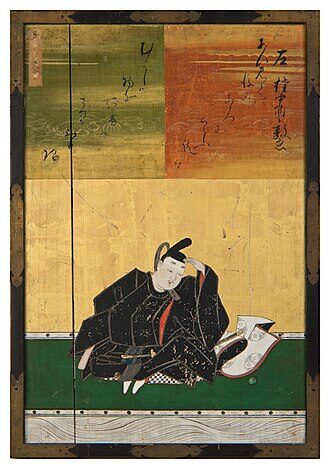
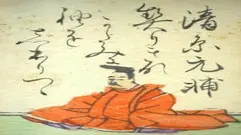
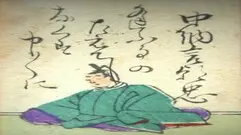
コメント