↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
36番 清原深養父(きよはらのふかやぶ) 『古今集』
夏の夜は まだ宵ながら 明けぬるを
雲のいづこに 月宿るらむ
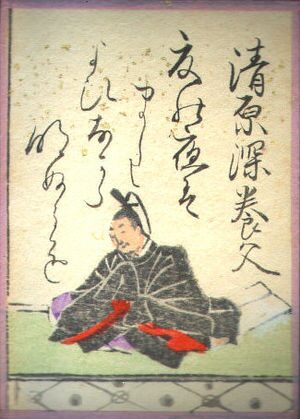
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
夏の夜はまだ夕暮れ時のような宵の時間なのに、もう夜明けになってしまった。
そんな中で、あの雲のどこに月が隠れているのだろうか。
語句解説
【夏の夜は】
助詞「は」は、他とは区別する意味があります。
「夏の夜というものは」というような区別した意味があります。
【まだ宵(よひ)ながら】
「宵(よひ)」は夕暮れの時間帯、夜の初めの頃。
夏なら午後7時から9時くらいの時間。
【明けぬるを】
動詞「明く(あく)」の連用形+完了の助動詞「ぬ」+連体形。
「明く」は夜が明ける、「ぬ」は完了を示す。
接続助詞「を」は順接となり、「~ので」という意味。
【雲のいづこに】
「いづこ」は、「どこに?」という意味。
場所を尋ねる言葉。
【月宿(やど)るらむ】
「宿る」は「とどまる」「止まる」「隠れる」「存在する」の意味。
助動詞「らむ」は、現在推量で、「今は見えないが今ごろ~しているだろう」の意味。
「どの雲に隠れているのか」という、作者が目にしている光景を現在推量として、月を人間になぞらえる擬人法で「どの雲に宿をとっているのだ」と表現しています。
作者: 清原深養父
清原深養父(きよはらのふかやぶ) 〈生没年 不詳〉
平安時代前期の歌人で、『古今和歌集』の撰者たちとほぼ同時代に活躍しました。
姓からも分かる通り、学問や文学に優れた清原氏の一族に属し、彼自身も教養豊かな人物だったと考えられています。
藤原兼輔・紀貫之・凡河内躬恒などの歌人と交流があり、彼の和歌の才能が周囲に認められてい当た事が分かります。
↓紀貫之・凡河内躬恒の和歌を解説しています、ぜひご覧ください!↓
清原深養父は官人としても活動しており、文才と共に公的な職務をこなす実務的な側面もありました。
息子には同じく著名な歌人であり『後撰和歌集』の撰者でもある清原元輔がいます。
さらにその孫が清少納言であることからも、彼の家系がいかに文学的素養に富んでいたかが伺えます。
彼の作品は『古今和歌集』や『後撰和歌集』などに収録され、自然や感情を繊細にとらえた表現に優れ、当時の貴族社会においても高い評価を受けていました。
洗練された言葉選びと情趣豊かな感性が、後の和歌の伝統にも影響を与えた重要な歌人の一人です。
鑑賞:短い夏の夜、月の行方は🌕
夏の夜の儚さと、美しい自然への繊細な眼差しが込められた一首です。
夏は昼が長く夜が短い為、ようやく夜が訪れたと思った矢先にもう明けてしまうという、その時間の速さに対する驚きと、どこか寂しさ表現されています。
「まだ宵ながら明けぬるを」という表現には、「夜を楽しむ間もなく朝が来てしまった」という心情が込められており、時間の流れの儚さをしみじみと感じさせます。
また、「月宿るらむ」と月の行方を雲の中に探す場面には、月を単なる天体としてではなく、心を寄せる存在として見つめる優しい感性が表れています。
見えない月に思いを馳せることで、見えないもの・過ぎていくものへの愛惜の気持ちも重ねられています。
季節の移ろいや時間の儚さ、自然の中に感じる情緒が静かに美しく描かれており、彼ならではの風情と感受性を味わえる一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

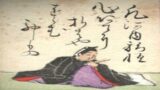
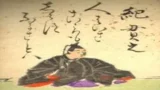
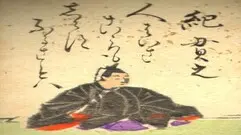

コメント