↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
32番 春道列樹(はるみちのつらき) 『古今集』
山川(やまがわ)に 風のかけたる しがらみは
流れもあへぬ 紅葉なりけり
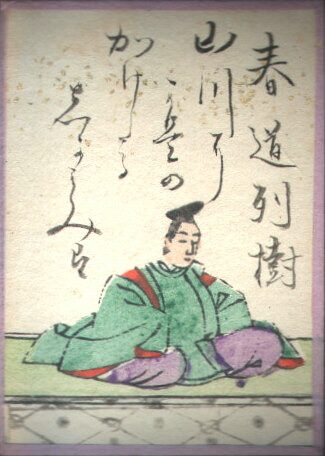
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
山の川に風がかけた柵(しがらみ)は、
流れきれずに留まっている紅葉であったのだなあ。
語句解説
【山川(やまがわ)】
山間を流れる川。(この意味超重要!!)
「やまがわ」という読みが重要で、「やまかわ」と読むと「山と川」という意味になり、意味が変わってしまう。
【風のかけたる】
「かけたり」の連体形。
「かける」は「設ける・作る」という意味で、ここでは風が自然に「しがらみ」を作ったという比喩。
【しがらみ】
流れをせき止める柵や杭。
古くは枝や木を使った簡易的な堰(せき)のこと。
ここでは紅葉の葉が溜まって柵のようになっている様子を表現。
少し分かりにくいですが、真ん中らへんにある編みこまれている物がしがらみ。
〈画像:Wikimedia Commons〉
【流れもあへぬ】
「流れようとしても流れきれない」という意味。
「あふ(敢ふ)」の未然形+打消しの助動詞「ぬ」。
「も」は副助詞で、「~さえ、~までも」という強調のニュアンス。
ここでは「~しきれない」「~できない」という意味。
【紅葉なりけり】
「なり」は断定の助動詞、「けり」は過去や詠嘆の助動詞。
「~であったのだなあ」と感動を込めた言い回し。
作者: 春道列樹
春道列樹(はるみちのつらき)〈生没年 不詳〉
平安時代中期の歌人で、系譜や詳細な経歴についてはあまり記録が残っておらず、謎の多い人物です。
『古今和歌集』や『拾遺和歌集』といった勅撰和歌集に作品が収められており、その詩才は高く評価されていた事が伺えます。
特に『古今和歌集』では、自然や四季の移ろいを巧みに詠んだ繊細な歌が多く、春道列樹の名を知らしめるキッカケとなりました。
また、彼の姓「春道(はるみち)」は当時としては珍しく、その出自については諸説ありますが、貴族ではなく中流の官人階級に属していた可能性が高いと考えられています。
その為宮廷の中心にいたわけではありませんが、和歌という文化活動を通して名を残すことができた、いわば「文芸で名を成した人物」の一人と言えるでしょう。
鑑賞:自然の造形を、細やかな気づきから🍁
山の川に吹く風によって、紅葉が集まって川をせき止めるように溜まっている様子を詠んだ一首です。
紅葉が川に浮かびながらも流れきれず、自然に「しがらみ(柵)」のようになっている光景は、まるで風がわざと柵を作ったかのような錯覚を引き起こします。
自然が意図せず生み出す美しさや造形を、人の手によるもののように見立てたこの歌は、古今集らしい繊細な感性が感じられる一首です。
「紅葉なりけり」という結句には、「これは紅葉だったのだなあ」と気づく瞬間の感動や余韻が込められており、しみじみとした自然の美への感動が映し出されています。
紅葉の美しさだけでなく、それが風に運ばれ川に溜まり、流れをせき止めるという一連の自然現象を詠み込むことで、季節の移ろいと時間の流れも感じさせます。
人工物ではなく、自然そのものが生み出した「しがらみ」であるという意外性が、読者に新たな視点を与えてくれる歌でもあります。
平安時代の人々がいかに自然を細やかに観察し、そこに美を見出していたかがよく伝わる風雅な作品です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


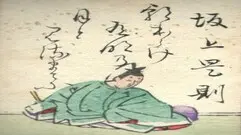
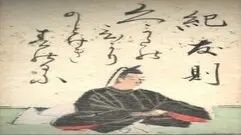
コメント