↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
30番 壬生忠岑(みぶのただみね) 『古今集』
有明の つれなく見えし 別れより
暁ばかり 憂きものはなし
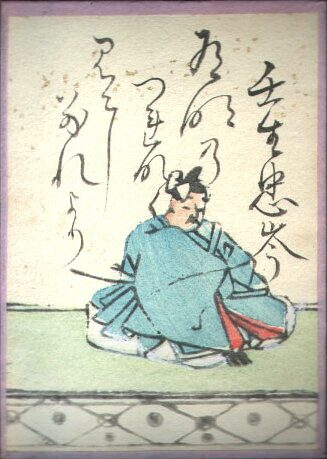
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
有明の月が残る明け方に、そっけなく別れたあの時から、
暁(あかつき=夜明け)ほどつらく、物悲しいものは他にない。
語句解説
【有明の(ありあけの)】
夜が明けても空に残っている月。
恋人と別れた後の「名残の時間」や「未練」を象徴することが多く、和歌では別れや物思いとよく結びつきます。
【つれなく見えし】
「つれなく」= 冷淡に、そっけなく。
「見えし」=見えた、思われたの意味。
「見ゆ」の連用形+過去の助動詞「き」
【別れより】
別れた時から。
「より」は起点を表す助詞で、「〜の時からずっと」というニュアンスになります。
【暁(あかつき)ばかり】
「暁」=夜明け、明け方。
恋人が人目を避けて帰っていく時間帯を指すことも多く、恋の終わりや寂しさの象徴です。
「ばかり」=~ほど、~くらい。
程度を表す言葉です。
【憂き(うき)ものはなし】
「憂き」=つらい、悲しい、苦しい。
感情的な苦しみや辛さを表す形容詞。
「ものはなし」=「~ほどつらいものはない。」の意味。
「もの」は漠然とした事柄・存在、「なし」は打消し(否定)を意味します。
全体として最上級の否定表現になり、「これ以上のものはない=最も○○だ」という形になります。
作者: 壬生忠岑
壬生忠岑(みぶのただみね) 〈生没年 不詳〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代前期の歌人で、「三十六歌仙」の一人としても名を連ねています。
壬生忠岑は、歌人としての評価が高く、勅撰和歌集『古今和歌集』の選者の一人に任命されました。
当時の和歌界では、紀貫之・凡河内躬恒らと並ぶ重要な存在であり、宮廷文化の中でも高い教養と感性をもって活動していたことが伺えます。
↓凡河内躬恒の和歌を解説しています、こちらもご覧ください↓
官職としては大きな地位には就いていなかったものの、和歌の才によって広く名を知られ、文化的な貢献を果たしました。
彼の作風は、繊細な感情表現と自然描写を巧みに組み合わせたもので、後の時代の歌人たちにも大きな影響を与えました。
平安貴族の教養の中心とも言える和歌を通して、時代の美意識や人々の心情を豊かに表現した、優れた文化人といえます。
鑑賞:悲しみの訪れ、毎日の夜明けから😞
この歌の核心は、「暁(あかつき)=夜明け」がもたらす寂しさです。
有明の月がまだ空に残る薄明かりの中、冷たく感じられた別れの瞬間が強く作者の心に刻まれました。
その時から「夜明け」という時間帯が、最もつらく心を苦しめるものになってしまったと語られています。
「つれなく見えし」という表現からは、相手が自分に対して冷淡で、心が通じ合っていないように感じた切なさが滲み出ています。
それは実際に相手が冷たかったのか、それとも別れのつらさの中でそう感じてしまったのか――いずれにしても、別れ際の一瞬が心に深く残っている事が分かります。
「暁ばかり憂きものはなし」という結句では、その後も夜明けの度に別れの記憶が蘇り、憂鬱な思いに捉われる日々が続いている事が暗示されています。
夜明けは本来新しい一日の始まりであるはずなのに、この和歌では恋の終わりを思い出させる時間として描かれており、そこに逆説的な美しさと哀しみがあります。
時間の経過とともに忘れられるどころか、暁という毎日訪れる時間に苦しめられる、そんな恋の苦しみを静かに、しかし鋭く訴える一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた


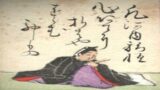
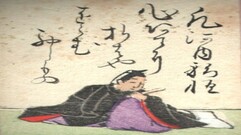
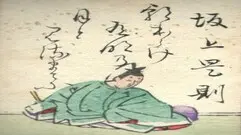
コメント