↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
25番 三条右大臣(さんじょううだいじん) 『後撰集』
名にし負はば 逢坂山(あふさかやま)の さねかづら
人に知られで くるよしもがな
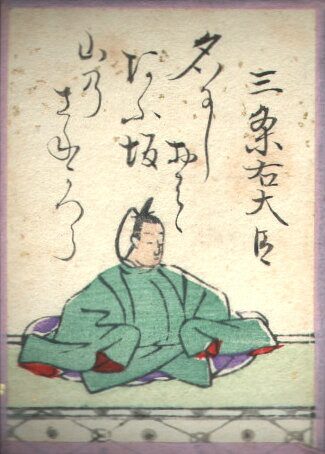
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
「逢う」という名前をもつ逢坂山のように、名前通りに誰にも知られずにあなたを
連れ出せるツタ(さねかづら)のような手段があればいいのに。
語句解説
【名にし負はば】
「名にし負はば」=「その名を持っているのならば」という意味。
「し」=強意の副助詞。
未然形に接続助詞「ば」が付くと、順接の仮定条件を表し、「~ならば」という仮定の意味を表します。
【逢坂山(あふさかやま)】
山城国(現在の京都府)と近江国(現在の滋賀県)の国境にあった山。
〈画像:Wikimedia Commons〉
「逢う」ことの象徴としても用いられ、恋の歌でよく使われる場所。
ここでは「逢う」という言葉と、実在する「逢坂山」の掛詞になっています。
【さねかずら(実葛)】(下の写真)
山野に生えるツタ(蔓)植物。
長く伸びるつるが「道筋」や「手段」の象徴として使われる。
〈画像:Wikimedia Commons〉
【人に知られで】
「で」は打消の接続助詞で、「人」は「他の人」という意味。
「他人に知られないで」という願望を表している。
【来るよしもがな】
「来る」=「来ること」、「よし」=「由」で「手段・方法」を表す。
「〜もがな」は「〜があったらいいのになぁ」という願望の終助詞。
「(こっそりあなたのもとに)来る方法があればいいのに」という意味。
作者: 三条右大臣(藤原定方)
藤原定方(ふじわらのさだかた)〈873年〜932年〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代中期の貴族であり、藤原北家・魚名流(うおなりゅう)という一族に生まれました。
藤原定方は藤原氏の中でもやや傍流の家柄ですが、本人の才覚や教養、人柄の良さによって信頼され、朝廷内で出世していきます。
定方は非常に教養豊かな人物で、漢詩や和歌を嗜み文化面でも存在感を示しました。
貴族社会において教養は大きな力であり、文人政治家として尊敬を集めていました。
彼の政治的立場は、同じく藤原氏の中心勢力である藤原時平(道真を左遷した人物)とは異なり穏健派であり、左遷された菅原道真の名誉回復に尽力したとも言われています。
菅原道真の死後、彼に対する同情が高まる中で、菅原道真を評価しようとする動きに関わった人物の一人です。
↓菅原道真の句も解説しています、ぜひご覧ください!↓
鑑賞:秘めた恋心、誰にも知らずに🔒
人目を避けてでも愛しい人に会いたいという、切実な恋心を詠んだ一首です。
冒頭の「名にし負はば」は、逢坂山という地名が「逢う」という意味を持つことにかけています。
「その名にふさわしく、本当に「逢う」ことをかなえてくれる山ならば…」という願いが込められています。
「さねかづら」は山に自生するツル性植物で、つるをたどって進むイメージがあります。
今回は恋しい人の元へ忍んで行く、道筋や手段の象徴として用いられています。
「来るよしもがな」は、「来る方法があればよいのに」と、現実には叶わない願いを切なく表現しています。
自然や地名に言葉を重ね、恋心を遠回しに深く表現しているのが、この歌の魅力です。
逢いたくても逢えないもどかしさと、せめて気持ちだけでも届いてほしいという想いが、静かに胸を打ちます。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた



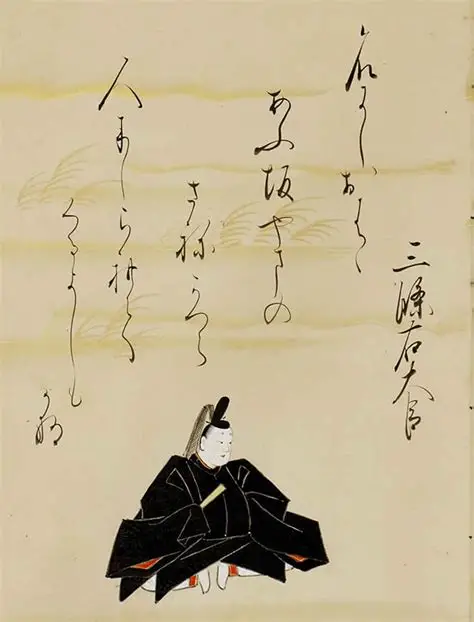
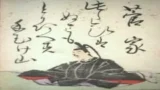
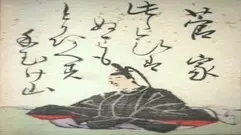
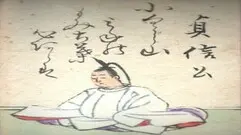
コメント