↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
22番 文屋康秀(ふんやのやすひで) 『古今集』
吹くからに 秋の草木(くさき)の しをるれば
むべ山風を 嵐といふらむ
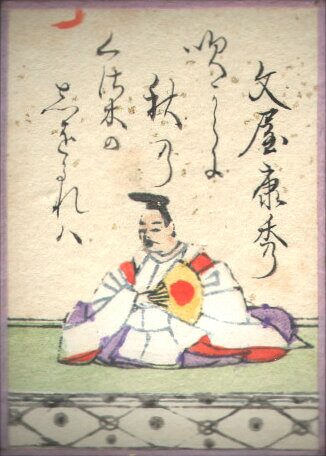
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
秋の草木が風に吹かれてしおれているので、
なるほど山風(やまかぜ)を「嵐」と呼ぶのだろう。
語句解説
【吹くからに】
吹く=「風が吹く」の意味。
からに=「〜するときに」「〜するとすぐに」の意味。
動作の直後を表す。
【草木(くさき)の】
草木(くさき):草や木。
植物の総称。
【しをるれば】
しをる=萎れる(しおれる)、枯れる。
れば=理由・原因を示す接続助詞。
「〜ので」「〜だから」の意味。
【むべ】
「なるほど」「当然だ」「やはり」という意味の副詞。
感嘆を表す。
【山風(やまかぜ)を】
山風=「山から吹く風」。
特に秋の強い風のこと。
【嵐といふらむ】
嵐(あらし)=「強い風や暴風雨」。
ここでは強風の意味。
秋の季語でもあり、夜明けが近いことを表す。
「いふ」=「言う」。
「らむ」=「〜だろう」「〜に違いない」という推量の助動詞。
作者: 文屋康秀
文屋康秀(ふんやのやすひで)〈生没年 不詳〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代前期の貴族・歌人で、「六歌仙」の一人として名を残す人物です。
陽成天皇の元で朝廷に仕えました。
↓陽成天皇の和歌を解説しています、こちらもご覧ください!↓
『古今和歌集』を代表する技巧派の歌人で、当時の歌壇(和歌を詠む人々の社会的な集まりや活動の場)では一定の地位を築いていました。
彼の出自は文屋氏という比較的新興の家系で、家格としてはそれほど高くなかったとされます。
ただ、歌の才に恵まれており、和歌によってその名を世に残しました。
紀貫之が書いた『古今和歌集』の「仮名序」では、「言は巧みにして心少なし(ことばはうまいが、心が乏しい)」と評され、いわば「技巧は光るが情が浅い」といった評価を受けています。
これは言葉の選び方や比喩がうまい一方で、感情の深みや余韻に欠けるという意味合いです。
とはいえ、このような批評も彼の存在感を物語るものであり、当時の文化サークルの中で注目されていた証です。
現在では、理知的で構成力のある歌風が再評価され、感情だけに頼らない洗練された表現の先駆者とも見なされています。
感性だけでなく「理性」で自然や感情を捉え、それを言葉で表現するスタイルを確立し、のちの和歌の発展にも影響を与えました。
鑑賞:新しい発見、秋の自然から🍂
秋の風景を通して自然の摂理と人間の感性の繋がりを巧みに描き出した一首です。
文屋康秀は風が吹くとすぐに草木がしおれる様子を観察し、「なるほど、だから山風のことを“嵐”と呼ぶのだな」と納得しています。
「吹くからに」は風が吹いた瞬間という意味で、秋の訪れが急激である事や自然の変化が一瞬である事を強調しています。
秋風が草木を一気にしおれさせる描写は、季節の移ろいの儚さや無常観を強く印象付けます。
「むべ」は古語で「なるほど」「いかにも」と納得する意味で使われ、風の激しさに「嵐」という名が付けられた理由に深く感心しています。
「嵐」という言葉にただの気象現象以上の意味を見出し、自然の姿と日本語の感性の鋭さを重ねている点が秀逸なのです。
静かに吹く風に秋の気配を感じ、そこに言葉の由来を重ね合わせる繊細な心の動きが、平安時代の貴族の教養と美意識を象徴しています。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

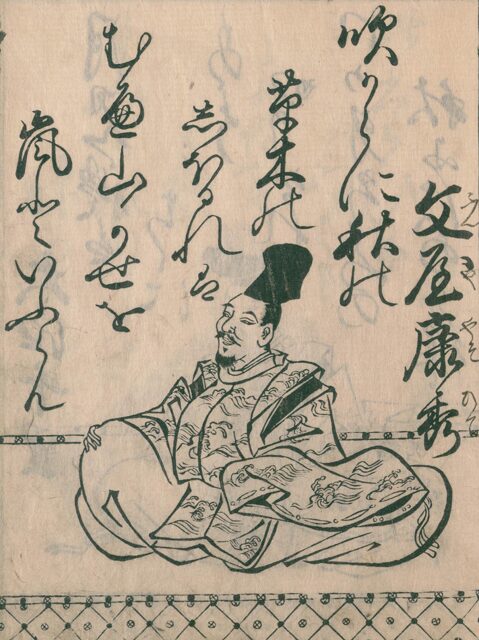

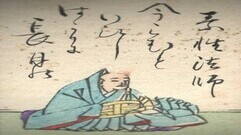
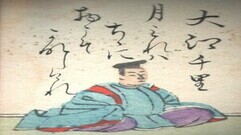
コメント