↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
21番 素性法師(そせいほうし) 『古今集』
今来むと 言ひしばかりに 長月(ながつき)の
有明(ありあけ)の月を 待ち出(い)でつるかな
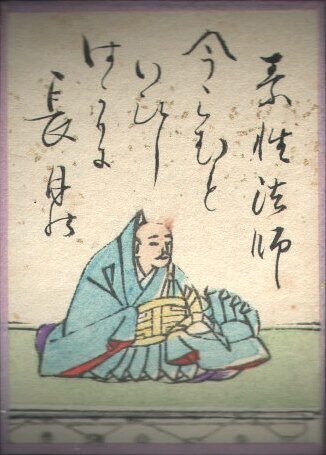
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
すぐ来るよ、とあなたが言ったばかりに、
私は秋(9月)の明け方の月が出るまで、ずっと待ってしまいましたよ。
語句解説
【今来む(いまこむ)】
「来(こ)」+意志の助動詞「む」。
「む」は話し手の意志や推量を表す。
ここでは恋人の発言とされる。
【と】
「~と」を表す引用の格助詞。
発言内容を表す。
【言いし】
動詞「言ふ」の連体形+過去の助動詞「き」の連体形「し」。
「言った(あなたが)」という意味。
【ばかりに】
接続助詞的に使われ、「それだけを理由にして」と原因・理由を表す。
残念な気持ちがにじむ言い回し。
【長月(ながつき)の】
「長月」=「旧暦9月のこと」
秋の終わりを示しています
「の」は格助詞で、次の「月」にかかる。
【有明の月(ありあけのつき)】
夜が明けても空に残っている月(明け方の月)
秋の季語でもあり、夜明けが近いことを表す。
遅い時間まで待った象徴。
【待ち出でつる(まちいでつる)】
「待ち出づ」=「待ち明かす」の古語的表現。
「つる」は完了の助動詞「つ」の連体形で、過去の意味。
全体で「(結局)待ってしまった」というニュアンス。
【かな】
「かな」= 詠嘆の終助詞。
「~だなあ」と感動を表す。
作者:素性法師
素性法師(そせいほうし)〈生没年 不詳〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代前期の歌人・僧侶で、俗名(出家前の名前)は不明です。
父は有名な歌人である僧正遍昭(そうしょうそうしょうへんじょう)で、六歌仙の一人に数えられるほどの人物です。
↓僧正遍昭も百人一首に登録されています!、ぜひご覧ください!↓
素性法師は出家して仏門に入り、京都を中心に暮らしていたとされます。
宮廷歌人として活動し、多くの和歌を残しました。
彼の歌は『古今和歌集』や『後撰和歌集』などの勅撰和歌集にも収められており、優美で感情表現の豊かな作品が多いのが特徴です。
恋の歌を得意とし、この歌のように「切なさ」や「期待が裏切られる悲しみ」など、繊細な心の動きを詠むのが上手でした。
僧侶でありながら、俗世の情(恋や人間関係)を深く理解していた人物であり、その心の深さが和歌に表れています。
素性法師は宗教者でありながら、恋や人生の機微を表現する事で、平安時代の感性を今に伝える重要な歌人の一人と言えるでしょう。
鑑賞:忘れられない貴方の言葉と秋の訪れ🌕
恋人の「すぐ行くよ」という言葉を信じて待ち続けたものの、遂に夜が明けてしまったという、切ない恋の気持ちを詠んだものです。
表面的には何気ない場面のようですが、言葉の裏には深い感情が込められています。
まず、「今来む」という一言が、作者にとってどれほどの重みを持っていたか、「有明の月を待ち出でつるかな」という結びに強く表れています。
「有明の月」は、夜がすっかり明けてしまうほどの時間の経過を象徴しています。
期待して待っていたのに相手は来ず、しかもその期待は一言の言葉に過ぎませんでした。
そんな「信じた者の苦しさ」が、静かに言葉に滲み出ています。
待ちわびる夜の冷たさ・心細さ・あきらめの感情が、秋の終わりの空気と共に伝わってきます。
作者は僧侶であり、我々から遠い存在の様に感じるかもしれませんが、この歌からは世俗の恋に深く心を動かされた繊細で、身近な存在の様に感じます。
人の心の儚さや言葉の軽さ、そして信じてしまう自分の弱さを込められた、読む者の心にもじんわりと染み込んでくる作品なのです。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた

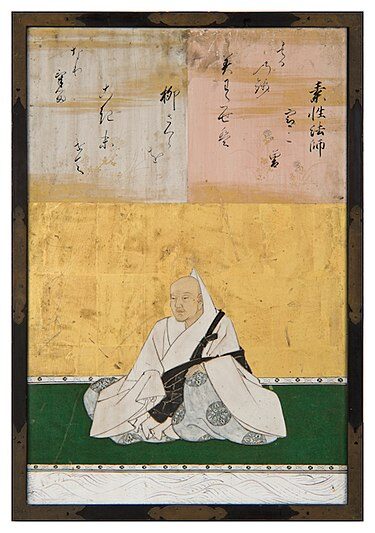
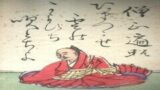
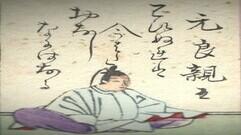
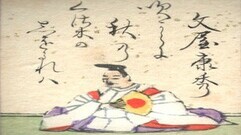
コメント