↓百人一首始めてみませんか!!!↓

https://amzn.to/4nqj9do(小倉百人一首 小倉山(寛政12年創業のかるたの老舗・大石天狗堂)
今回の和歌
5番 猿丸太夫(さるまるだゆう) 『古今集』
奥山(おくやま)に 紅葉踏みわけ 鳴く鹿の
声きく時ぞ 秋は悲しき
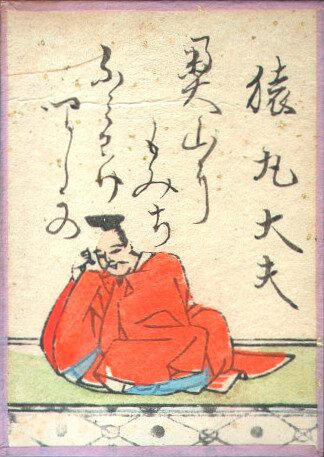
〈画像:Wikimedia Commons〉
現代語訳
現代語訳
人里離れた深い山で、紅葉を踏み分けて鳴く鹿の声を聞いた時こそ、
秋は本当にもの悲しいと感じる。
語句解説
【奥山(おくやま)に】
人里離れた深い山。
【紅葉踏みわけ】
踏み分ける(紅葉を踏んで進む)の意味。
〈画像:Wikimedia Commons〉
今回の山の場所は分かっていませんが、こんな紅葉している山を作者は想像していたのだと思います。
【鳴く鹿の声聞くときぞ】
「鹿の鳴き声を聞くときは」という意味です。
〈画像:Wikimedia Commons〉
この時代都は平安京(京都)にありましたが、現在の奈良公園のような鹿を見て、作者はこの歌を作ったのかもしれませんね。
「ぞ」は強意の係助詞で、この後の「悲しき」と結んでいます。
【悲しき】
形容詞「悲し」の連体形。
「悲しい」の意味。
「ぞ」と結ばれているので、文末ですが終止形ではなく、連体形なのに注目です。
作者:猿丸太夫
猿丸太夫 (さるまるだゆう)〈生没年 不詳〉
〈画像:Wikimedia Commons〉
平安時代初期の歌人であり、『百人一首』や『古今和歌集』にその名が残る人物です。
ただし、正確な生没年や経歴も分かっておらず、その人物像や実際の活動については殆ど記録がありません。
「猿丸太夫」という名も実名ではなく、仮の名前だった可能性があります。
その為、歴史上の人物というよりは、伝説的な歌人として語られる事が多いです。
彼の作風は技巧に走ることなく、素朴でありながら深い感情を讃えています。
自然の中にある哀しみや美しさを、まるで目の前に広がる風景のように詠むのが猿丸太夫の特徴です。
彼は後に、平安時代の歌人の中でも特に優れた三十六人を選んだ「三十六歌仙」の一人にも数えられています。
限られた作品の中に、日本人の自然観や感情表現の原点を見ることが出来る、非常に印象深い存在です。
鑑賞:鹿の生命と秋の悲しさ 🦌
秋の深まりと共に感じられる物悲しさを、山奥の自然の情景を通して詠んだものです。
人里離れた奥山で、紅葉を踏み分けながら鳴いている鹿の声が響くその瞬間に、作者は秋の寂しさを強く実感します。
紅葉の美しさと、鹿の切ない鳴き声という視覚と聴覚の両面から、秋の情趣が深く描かれています。
特に「鳴く鹿の声」は、古来より恋しさや孤独の象徴とされており、この歌でもそうした感情が色濃くにじみ出ています。
「時ぞ秋は悲しき」という表現には、「まさにこの時こそが秋の哀しさを最も感じさせるのだ」という強い心の動きが表れており、読者の感情にも静かに訴えかけてきます。
自然の中に身を置くことで、季節の移ろいや人生の儚さをしみじみと感じるという、日本人特有の美意識がよく表れている一首です。
↓久しぶりに百人一首やりたい方はオススメです!独特の緊迫感を味わえます↓

百人一首 小倉百人一首CD付 【舞楽】 新年 新春 遊び 札遊び お正月 百人一首 全日本かるた協会専任読手 朗詠CD付 ちはやふる かるた遊



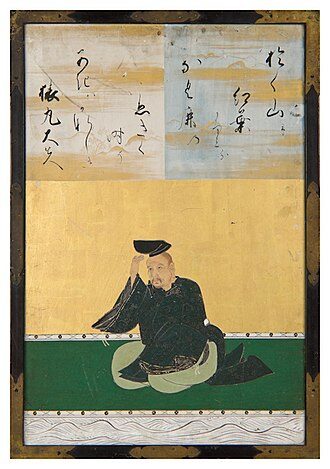

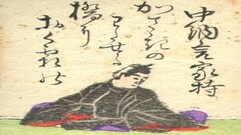
コメント