皆さんこんにちは!
今回は平安時代初期のスーパースター、桓武天皇について紹介します!
仏教との関係性に注目すると、理解が早まります。
約1000年間、都が置かれた京都の土台を作った桓武天皇を学んでいきましょう!
↓平安時代までの流れを知りたい方は、こちらをご覧ください!!↓
奈良時代の終焉
〈781年 桓武天皇 即位〉
「桓武天皇」が第50代天皇として、平城京で即位しました。
本名は「山部親王(やまべしんのう)」と言います。

〈桓武天皇:Wikimedia Commons〉
お父さんは「光仁天皇」です。
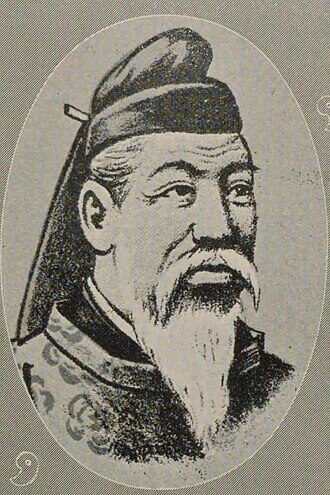
〈光仁天皇:Wikimedia Commons〉
「天武天皇」即位以来、長らく天武系の血筋が皇統を継いでいました。
「光仁天皇」は「天智天皇」の孫にあたる人物なので、天智系の血筋だと覚えておきましょう!

〈天智天皇:Wikimedia Commons〉
「光仁天皇」のお母さんは「高野新笠(たかののにいがさ)」と言い、朝鮮半島から来た渡来人の血を引いていたとされる人です。
つまり、「桓武天皇」は、天智系の血筋であり外国のルーツもある、非常に異色の天皇なのです。
「桓武天皇」の即位にあたり批判の声が沢山挙がったので、多くのライバルを排除し権力基盤を固める為に動き始めます。
〈784年 長岡京 遷都〉
桓武天皇が即位した場所は「平城京」です。
「平城京」は天武系の象徴とも言うべき都なので、桓武天皇は遷都を考えたのです。
仏教勢力が強くなりすぎて、政治が上手く機能していなかったという理由もあります。
「藤原種継」を新しい都造営の最高責任者とし、交通の便がいい場所を探させました。
そこで見つけてきたのが、「長岡」の地でした。

桓武天皇は「長岡京」の造営を最優先事項として、急いで作らせました。
〈785年 藤原種継 暗殺〉
造営の最中、「藤原種継」が何者かに暗殺される事件が発生します。
犯人は皇太子の「早良親王」という噂が立ち始めます。
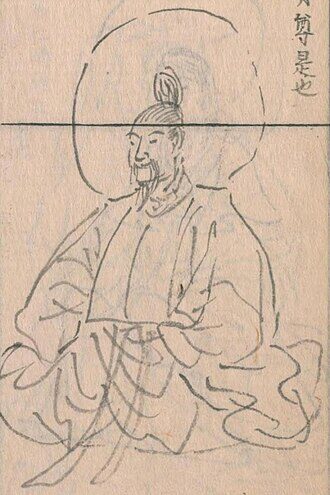
〈早良親王:Wikimedia Commons〉
「早良親王」は無実を主張しましたが、「桓武天皇」は処罰しました。
しかし数日後から、桓武天皇の周りの人が謎の死を遂げ始め、遂には皇后までも亡くなってしまいます。
飢饉や疫病も発生し、桓武天皇の息子も病気にかかります。
占い師に原因を占わせると「早良親王の怨霊」との結果が出ました。
桓武天皇は「長岡京」の造営を中止し、新たな場所を探しにいくのです。
〈792年 健児 採用〉
「健児(こんでい)」=「京都警備の志願者募集制度」です。
「大宝律令」で男性に規定されている税金として、京都の警備の労役は「衛士(えじ)」と言いました。
「衛士」は1年間警備を担当しなければならず、いつ選ばれるか分かりません。
単純に1年間家族の元を離れて労役を課されるので、農民の負担は尋常ではありません。
桓武天皇は「健児」を導入し、志願した人だけが京都の警備をする制度に変えました。
「衛士」を任命された人は「調・庸・雑徭」が免除されるので、独身男性は「衛士」の方が楽で志願する人も多かったようです。
平安時代の始まり
〈794年 平安京 遷都〉
新しい都こそ、現在の京都駅周辺の土地でした。
西に「桂川」、東に「鴨川」が流れる平安京は、水運の便も非常に良く、都に最適だったのです。
平安京に遷都した事により、平安時代の幕開けです。

〈平安京の模型:Wikimedia Commons〉
天武系の血筋の否定と、仏教による政治を刷新する為の新しい都です。
〈804年 坂上田村麻呂 征夷大将軍に就任〉
桓武天皇は政治や都のことだけでなく、「日本を豊かにする」為に、戦いにも力を入れました。
東北地方では「蝦夷(えみし)」と呼ばれる人々が暮らしていて、独立した国のような感じになっていました。
朝廷の命令に従わず、税金を納めない事も多かったようです。
桓武天皇は軍隊を送って東北地方を治め、税収を強化しようとしました。
この戦いで活躍したのが、「坂上田村麻呂(さかのうえのたむらまろ)」です。

〈坂上田村麻呂:Wikimedia Commons〉
「坂上田村麻呂」は日本で初めて「征夷大将軍」になった人物です。
「征夷大将軍」は桓武天皇が新しく新設した役職であり、当時の法律である「大宝律令」には記載されていません。
律令に記載されていない役職を「令外官(りょうげのかん)」と言います。
「征夷大将軍」は現在、武士のトップという意味合いが強いと思います。
「征夷」は「蝦夷を征伐する」という意味が込められているので、当時はただの1つの役職に過ぎませんでした。
日本最初の幕府を開いた源頼朝が「征夷大将軍」の役職を天皇に求めたのは、「令外官」だからです。
「律令」という「貴族が守るルール」から一線を画す「令外官」だからこそ、武士の自分にふさわしいと考えていたのです。
〈797年 勘解由使 設置〉
当時の政治の仕組みとして、各国に「国司」を派遣していました。
詳しい内容は分かっていませんが、「国司」の交代の時に、色々トラブルが発生していました。
国司交代の引継ぎの際、トラブルが無いように監視する「勘解由使」という役職を設置しました。
「勘解由使」も「征夷大将軍」と同じく「令外官」です
〈804年 最澄・空海 遣唐使として派遣〉
平城京時代の政治に口出しする仏教を避け、正しい仏教が広める事を狙いとした派遣です。
2人を遣唐使として中国に派遣し、「密教」と呼ばれる厳しい修行を要する仏教を持って帰ってこさせました。
旧仏教に対抗し厳しい仏教を流行らせ、修行を必要とさせる事で政治と仏教の分離を図りました。
↓最澄と空海については、こちらで詳しく解説しています!!↓
〈805年 徳政論争〉
「藤原緒嗣」と「菅原真道」に、桓武天皇の政治について真剣に討論させた出来事です。

〈藤原緒嗣:Wikimedia Commons〉
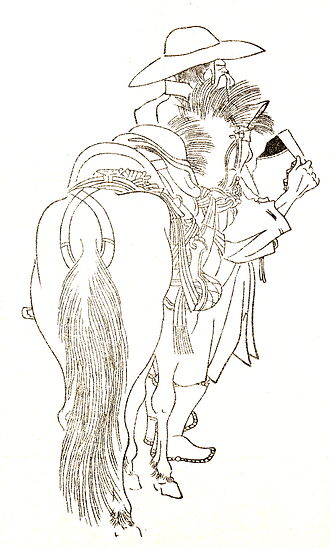
〈菅原真道:Wikimedia Commons〉
桓武天皇の二大政策は「造作」と「軍事」です。
「造作」=「平安京の造営」
「軍事」=「蝦夷の征討」
桓武天皇は「造作」と「軍事」をこのまま継続するべきかについて、農民の立場から考えて討論させたのです。
民に寄り添う優しい天皇だった事が分かりますね。
「藤原緒嗣」は中止を唱えました。
理由は「蝦夷の征討で人が死んでいるのに、長岡京から平安京の造営まで負担をかけすぎている」です。
「菅原真道」は継続を唱えました。
理由は「平安京という天皇の拠点が未完成では、天皇の権威が落ちる」です。
「桓武天皇」が選んだのは、「中止」でした。
異例の経歴で苦労してきた人だからこそ、農民の事情に寄り添った決断だったのかもしれません。
受験生の方へ
大学受験を迎えるに当たって、絶対に外せない書籍があります。
それが日本史一問一答です。
日本史一問一答【完全版】3rd edition [ 金谷 俊一郎 ]
今まで多くの日本史一問一答に目を通してきましたが、ダントツで使いやすいのが東進ブックス出版の一問一答です。
最難関大学にもバッチリ対応できる問題量で、共通テストの対策も勿論万全です。
以下が実際の例題です。
日蓮は[★★]教が仏法の正しい教えである事を悟り、
[★★★]を唱える事によって救われると説いた。
文章が虫食い形式になっており、虫食いの[]の中に星1〜3が書かれていて、一目で単語の重要度分かります。
例題の答えは、★★=法華、★★★=題目、となります。
私立大学にしろ、国公立大学にしろ、日本史受験をするなら絶対に必要になる書籍です。
学校のクラスを見渡すと、既に持っている人もいるのではないでしょうか。
自分が受ける大学の難易度に合わせて、勉強量を調節できる書籍なので、受験勉強のゴールを知る為にも、一回は目を通して欲しいです。
早めに対策した者が受験勉強を制します。
さぁ、日本史を楽しみましょう!






コメント